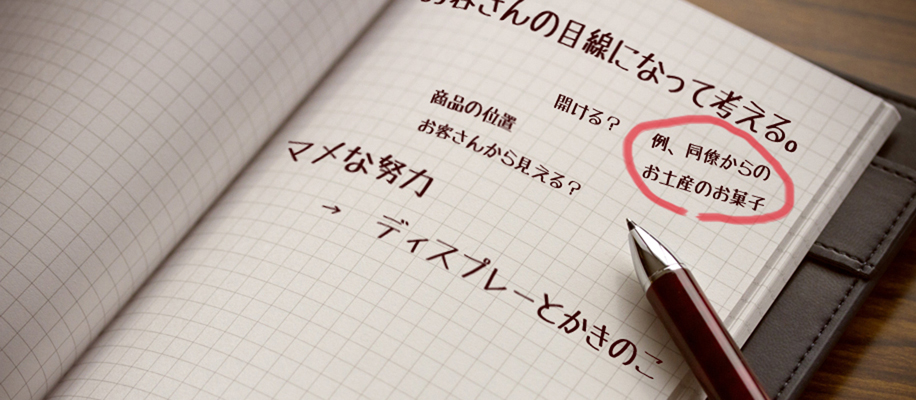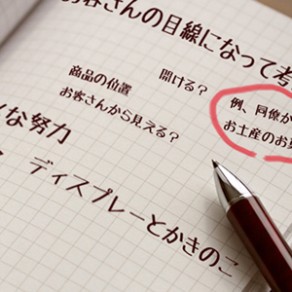涼花が質問をする、酒居が答える。このルーティーンとも言える流れが、涼花の油断を誘っていた。
「経営者からの相談で多いものってなんですか?」
「『三大悩み』と呼んでいるんですが、『コンセプト』『料金設定』『集客方法』ですね」
「なるほど……」
「ダメなサロンコンセプトで多いのは『抽象的すぎるコンセプト』で、例えば『美容と健康』みたいなコンセプトです。正直、それではやっていけません。もっとコンセプトを絞り込まないと」
「た、例えばどうやって……」
涼花は青ざめた。涼花の経営しているサロンのアピールポイントがまさしく「美容と健康」だったからだ。
「私の講義ではまず、経営者に『サロンをやろうと思った動機』を書いてもらいます。そこがコンセプトのコア(核)なので。『なんでアロマ?』『なんでエステ?』『人の役に立ちたいだけならボランティアでもいいでしょ?』そこを思い出してもらって、コンセプトを考えてもらいます」
涼花は自分がサロンを始めた時のことを思い出していた。酒居にとって、涼花の思い出している様が、よほど「ぼ~」っとしているように見えたのであろう。酒居の方から次の話題へと移行させた。
「次に、料金設定についてですが……」
「あ……はい!」
「料金設定は高い・低い以前に、自分のサロンの原価計算ができていない人が多すぎますね」
「げ、原価……計算? (したことない……)」
「時間経費、つまりサロンで1時間にかかる経費です。そこに利益をどう付与するかですね。マンションの一室で開業している人が、5年後にテナントを借りて経営するつもりなら、それに必要なプール金も加算しないといけません。それを踏まえた上で、料金設定をするのです。決して『他のサロンがこの料金だから、ウチもこの料金にしよう』という考えではダメです」
「う……」
涼花は謝罪したいと思った。酒居に対してではなく、これまでのサロンの客にでもなく、自分自身にでもなく、何かに謝罪したい気持ちになった。涼花は折れかかった気持ちを建て直し、質問を再開した。
「最後の、『集客』についても教えてください」
「はい、最近の集客はWEBが主流ですよね?」
「だと思います」
「でも残念ながら、私はWEBに関してはプロじゃないので……」
「……」
「ただ言えるのは、広告に『ウチのサロンは、ここがスゴイんです!』なんてものは必要ありません」
「え!? でも、スゴイところをアピールしないと……」
「広告を見た人に『すごいサロンだ!』って思わせるんじゃなくて『このサロンは私に必要だ』と思わせることが大切なんです」
「あ……確かにそうですね」
「もうひとつ大切なのはリピーターをつくることですね」
「でも、そのリピーターがなかなかできないんですよ」
「そうですね。自宅のサロンだと最初は、お客様はお友達がほとんどです。でも、お友達はお付き合いで来てくれるので、半年もすると全員いなくなると思った方がいいです」
――経験済です。
「だから、別のお友達を紹介してくれる人をどうやって作るか。そういう仕掛けの話を講義ではお話します」
「……そのお話は、していただけないんですか?」
「結構ですよ。その前にまず、あなたのサロンではどんなことをしていますか?」
「いやあ、私のサロンでは特に何も……はは♪」
酒居は笑顔で黙って涼花を見つめていた。涼花は照れ笑いをしながら酒居を見ていた。しかし、涼花の笑顔は徐に真顔に変わっていった。涼花は自分の背中を一筋の汗が流れていくのを感じた。
――やってしまった。
涼花は完全に油断していた。油断のために、涼花はカバンと財布を掴んで逃げるという行動に即座には移行できなかった。
「申し訳ございません!」
涼花には立ち上がり、頭を下げることしかできなかった。
「え!? 何を謝っているんですか?」
「わ、私はウソを吐いていました! 私は『月刊リラクゼーション』の記者でも、ニシジマという人物でも……」
酒居は涼花の言葉を遮るかのように言葉を返した。
「きっと……聞こえなかったんですよ」
「え?」
「あなたは……私に名前や職業を伝えましたか? 私に名刺を渡しましたか?」
「え……いや……」
「私が勝手にあなたのことを勘違いしただけ。私の『月刊リラクゼーションの西島さんですよね?』という言葉も、私の声が小さくて、あなたに聞こえなかったのよ」
涼花は溢れ出そうになる涙を堪えながら、やっぱり頭を下げることしかできなかった。
「あ……ありがとうございます!」
「さあ、そろそろ次の仕事の時間だから」
「あ、30分経ちますもんね。次の現場ってどこですか? そこまでご一緒させてくださいよ」