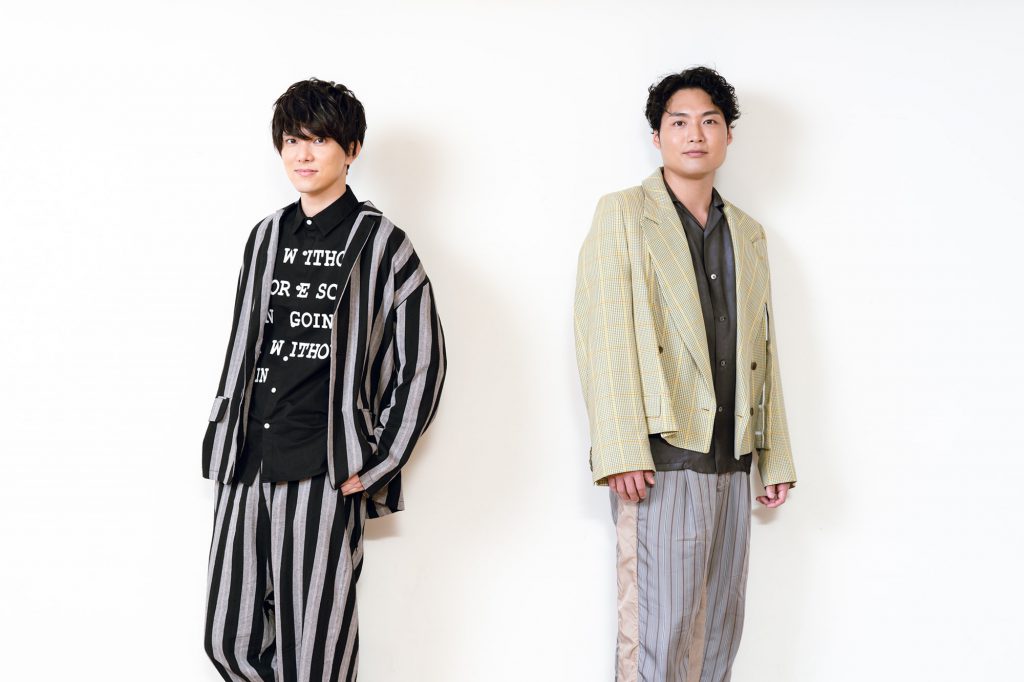地域包括支援センターとは? どんな役割があるの? 利用する2つのメリットを紹介
介護福祉を担う施設のなかのひとつに、地域包括支援センターがあります。地域包括支援センターという名前を聞いたことがあっても、「どんな施設なの?」「何が相談できるのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、地域包括センターについて紹介し、どんな役割を担っているのかや、利用するメリットについて解説します。
地域包括支援センターとは?

まずはじめに、地域包括センターとはどういった施設なのか、概要を見ていきましょう。
地域で高齢者の生活をサポートするために設置された施設
地域包括支援センターは、主に高齢者の健康や生活を地域で支えるために設置された施設です。
厚生労働省の発表によると、日本では65歳以上の高齢者の数が3,500万人を超えており、2042年には3,900万人のピークを迎え、さらに総人口に対する高齢者の割合は増加し続けることが予想されています。
こういった高齢者たちが、尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、厚生労働省では地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
その地域包括ケアシステムの中核となる施設が、地域包括支援センターです。
地域包括ケアシステムとは?
厚生労働省によると、「団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。」とあります。
つまり地域包括ケアシステムとは、医療・介護や生活などのさまざまな支援を一体的に提供し、その地域や自治体で高齢者をサポートしていけるシステムのことです。
居宅介護事業所とはどこが違うの?
地域包括支援センターと同じく高齢者の生活をサポートする施設に、居宅介護事業所があります。地域包括支援センターと居宅介護事業所の違いはどこにあるのでしょうか。
地域包括支援センターは、高齢者に関する総合的な相談を受け付けている施設です。高齢者自身やその家族のほかにも、近所に住む人からの相談も受け付けています。
一方、居宅介護事業所は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が常駐している事業所です。介護保険法に基づき、要介護認定者とその家族の生活環境や希望をもとにケアプランを作成したり、ケアプランに沿って介護保険サービス事業所と連絡や調整をおこないます。
どちらも高齢者の生活をサポートする施設ですが、おこなっているサポートの内容や対象に違いがあります。
地域包括支援センターはどこに設置されているの?
地域包括支援センターは、市町村が設置主体となっているため、全国の市町村に設置されており、令和4年4月末の時点で全国に5,404カ所あります。
本体のセンターである5,404カ所のうち、直営の施設は20%で、残りの80%は委託を受けた団体が運営しています。地域包括支援センターの委託先法人は、社会福祉法人・社会福祉協議会・医療法人などがあります。
なお、委託法人が運営しているセンターであっても、問い合わせは各市町村の介護保険担当窓口へするようにしましょう。
どんな専門家が支援に当たるの?
地域包括支援センターでは、保健師(看護師)、主任介護支援専門員・介護支援専門員、社会福祉士が、それぞれの役割に応じた業務に携わっています。保健師(看護師)の支援も受けられるため、社会福祉だけでなく、介護において医療的なサポートを受けたい場合も地域包括支援センターに相談してみてください。
どんな人が利用しているの?
地域包括支援センターの利用対象者は、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者の人や、高齢者の支援活動に関わっている人です。
高齢者本人の相談が難しい場合は、その家族が代理となってセンターへ相談することも可能です。ただし、高齢者と家族が離れて住んでいる場合は、「支援を必要とする本人」が住んでいる地域のセンターに相談する必要があるので注意してください。
地域包括支援センターの役割と業務とは?

地域包括支援センターは地域の高齢者やその家族、近所の人などからの総合相談窓口になることが主な役割です。その役割を果たすために、どんな業務をおこなっているのでしょうか?
ここからは、地域包括支援センターの役割と業務について簡単に紹介します。
地域包括支援センターの業務内容は、別記事でも紹介していますのであわせてご覧ください。
地域包括支援センターの業務内容を紹介|どんな相談が寄せられる? 今後の課題とは?
包括的支援事業
ひとつめは、幅広い介護の悩みや相談を受け付ける包括的支援事業です。例として4つの業務を紹介します。
1. 高齢者の相談窓口となる|介護に直面した家族にも
その地域に住む高齢者の、総合的な相談窓口として機能しています。高齢者本人だけでなく、介護に直面した家族、高齢者の近所の人などの相談にも乗ってもらえます。
2. 高齢者の権利を守る支援をおこなう|成年後見制度など
高齢者詐欺など消費者被害から守ったり、成年後見制度の周知や手続きをしたりするのも、地域包括支援センターの業務です。そのほかにも虐待被害の防止や対応など、高齢者のさまざまな権利を守る支援をおこなっています。
3. 介護予防ケアマネジメントを行う|介護予防サービスの案内など
介護が必要になった人だけでなく、介護予防の支援もおこないます。要支援認定を受けた人の介護予防ケアプランを作成したり、介護予防サービスの紹介をしたりして、自立した生活を続けられるようにサポートします。
4. 包括的で継続的なケアマネジメントの支援|介護支援専門員の支援
ケアの要である、介護支援専門員(ケアマネジャー)の後方支援も重要な業務です。介護支援専門員を対象とした研修会を開いたり、介護支援専門員同士の連携を強めたり、支援困難事例へのアドバイスなどをおこないます。
指定介護予防支援
介護保険制度の基本理念である「自立支援」にもとづき、要支援者が可能な限り自宅で自立した生活を送り、要介護状態となることを予防するために介護予防ケアマネジメントを行う事業者のことを、指定介護予防支援事業者といいます。
地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業者となることで、主体となって地域の老人介護支援センターや指定居宅介護支援事業者などと連携し、介護予防ケアマネジメントをおこなう必要があります。
地域包括支援センターを利用するメリットとは?

ここからは、地域包括支援センターの利用には、どんなメリットがあるのかを見ていきましょう。
1. 介護相談が無料でできる
地域包括支援センターは、基本的に無料で利用することができます。介護に関する相談を無料で専門家に対応してもらうのは、大きなメリットといえるでしょう。
2. 高齢者の関わる問題を早めに発見できる|虐待など
高齢者本人やその家族以外にも、その地域に住む人からの相談も受け付けることで、介護を通して起きる高齢者虐待など、問題の早期発見につながる効果があります。早期発見することで適切な処置への移行も早めにでき、高齢者の生活を守ることができます。
利用に注意点はある?
支援を利用する上での注意点として、センターでは直接介護を受けられるわけではないことがあげられます。地域包括支援センターの役割はあくまで支援に限るため、実際に受ける介護の詳細は、地域包括支援センターから紹介された介護事業所などに相談してみてください。
地域包括支援センターは高齢者福祉を支える地域の拠点

地域包括支援センターは、全国の市町村に設置されている、高齢者介護に関する支援センターです。高齢者本人はもちろん、家族やその地域に住んでいる人など、誰でも総合的な相談をすることができます。
地域包括支援センターには介護福祉に関わる専門家がいるため、相談内容によって適切な事業所を紹介してもらうことができます。地域の高齢者福祉を支える拠点として誰でも無料で利用することができるため、高齢者に関して気になることがあれば気軽に利用してみてください。
引用元
厚生労働省:地域包括支援センターについて
厚生労働省:地域包括ケアシステム
厚生労働省:3 地域包括支援センターの設置運営について(通知)
名古屋市社会福祉協議会:お仕事の紹介
袖ケ浦市:1 指定介護予防支援の概要
e-Gov法令検索:指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準