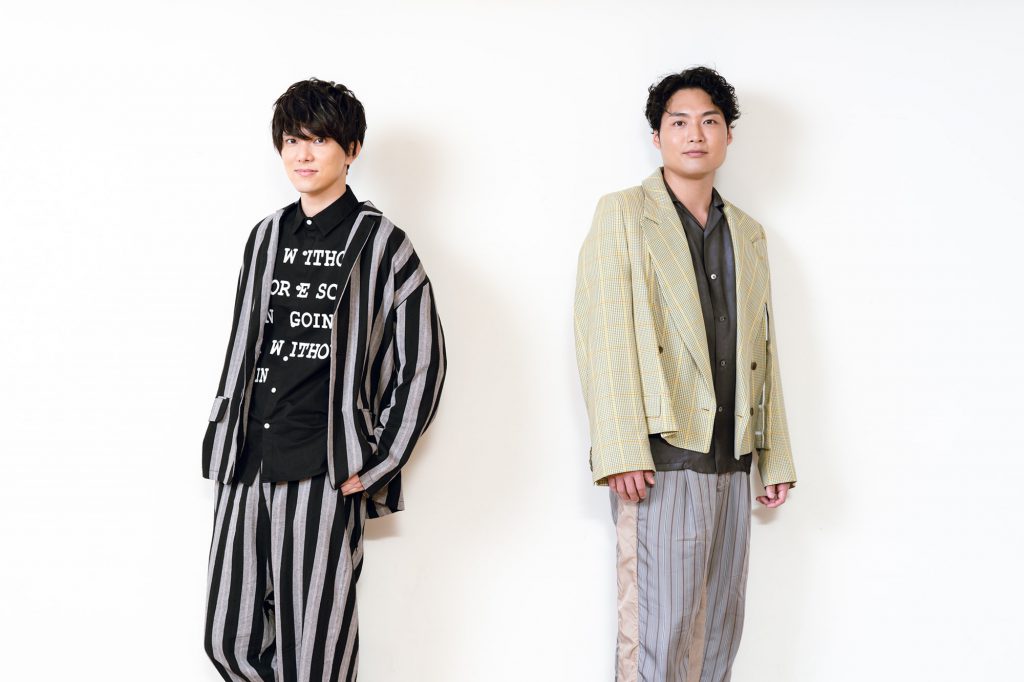ケアプランを作成する介護職員に資格は必要?ケアプランの種類や作成の流れを解説
ケアプランとは、これから介護を受ける方のために支援計画を立てることです。しかし、このケアプランは誰が作成するのでしょうか。また、作成に資格が必要なのかも気になるところです。
そこでここでは、ケアプランの作成に資格は必要なのか、プランの種類や作成の流れなどをご紹介します。
ケアプランとは?

上述したようにケアプランとは、要支援・要介護認定を受けた方が適切な介護保険サービスを受けるために作成する支援計画書のことです。
介護を必要とする方が自立した生活が送れるよう、本人やそのご家族の要望・状況などを踏まえて作成します。
ケアプラン作成業務をおこなうのに資格は必要?ケアプランの重要性とは
基本的に、計画の作成自体に資格は必要ないため、無資格者であっても介護職で採用されれば作成業務を担当できる可能性はあります。
ただし、求人では介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格保有者を条件とされることが多く、実際の作成業務も介護支援専門員が担当するのが一般的です。介護はチームでおこなうことが多いため、ケアプランを作成し、全員で共有して内容を理解することが重要となります。
計画作成担当者と介護支援専門員の業務内容の違い
計画作成担当者とは、介護支援計画の作成をおもな業務とするもののことですが、介護支援専門員の業務内容とどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、このふたつの仕事の違いをご紹介します。
計画作成担当者の業務内容
計画作成担当者のおもな業務内容は、利用するご本人やそのご家族から要望や相談ごとなどを事前にヒアリングし、さまざまな状況などを考慮したうえでプランを立案することです。
そのほかにも、プランどおり過不足なくサービスが提供できているのかといったチェック、必要であればプラン自体を見直すこともあります。また、実際に現場に出て介護をおこなうことも業務内容のひとつです。
ケアマネジャーの業務内容
介護支援専門員のおもな業務内容は、計画作成担当者とほぼ同じ内容といえます。両者の違いは、介護支援専門員という資格を有しているかどうかです。
ただ、施設によっては最低1名の介護支援専門員の資格保有者を配置しなければならないという人員配置基準があるため、やはり資格保有者のほうが有利であることは間違いありません。一般的に介護支援専門員の業務は、施設との橋渡しなど事務作業がメインとなっています。
ケアプランの種類

一口にケアプランといっても介護を受ける方が要介護者か要支援者かなどによって、作成するプランの種類は変わってくるのが特徴です。ここでは、それらの違いと特徴をご紹介します。
1. 居宅サービス計画書
対象が要介護1~5の認定を受けた人が該当するケアプランです。
居宅サービスというのは、在宅で介護をする人を対象としたサービス全般のことを指し、訪問、通所、短期入所、その他のサービスの4種類があります。そしてこれらの居宅サービスを利用する際に必要となるのが居宅サービス計画書です。
2. 施設サービス計画書
施設サービス計画とは、要介護1~5の認定を受けた人が対象で、居宅サービス計画と同様の対象者となります。
施設サービスとは、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3施設で受けられるサービスのことです。そして、この施設サービスを利用する際に必要となるのが施設サービス計画書になります。
3. 介護予防サービス計画書
介護予防サービス計画とは、要支援1・2の認定を受けた人を対象とするケアプランです。上記の2つとはサービスを受ける対象者が異なります。
介護予防サービスとは、その名のとおり介護までは必要ない高齢者が今後も要介護状態に陥らないよう、状態が悪化するのを予防するために提供されるサービスです。介護予防サービス計画書は、このサービスを受ける際に必要となります。
ケアプラン作成の手順、流れを解説

ケアプランは、介護サービスを利用するご本人やそのご家族の現状を理解し、ヒアリングなどの情報収集や会議をおこなって作成することが必要です。ここでは、プランの作成手順や流れについてご紹介します。
1. インテーク|利用者の情報収集
作成する際にまず必要となるのがインテークです。インテークとは、利用者の状況や要望、そしてそのご家族の要望などを把握するための情報収集のことをいいます。
利用者ご本人やそのご家族と対面でヒアリングする場合もあれば、電話でヒアリングする場合もあるなど、そのパターンはさまざまです。このインテークで得られた情報がプラン作成のもととなります。
2. アセスメント|情報の分析
インテークで得られた情報を分析するのが、アセスメントと呼ばれる作業です。アセスメントは、ケアプランの作成においてとても重要な作業で、利用者ひとりひとりに合ったプランを作成するためには、このアセスメントという作業をおろそかにできません。
利用者を単に介護度別にわけて同じサービスを提供するだけでは、利用者にとって最適なサービスとはいえないということです。
3. ケアプランの原案を作成
インテークで得た情報をアセスメントしたら、続いてはそれをもとに原案をまとめる作業です。利用者やそのご家族の要望に合わせた目標を設定し、それに対するサービスの検討、プランの組み立てをし、ケアプランの原案を作成します。
そして作成したケアプランの原案をもとに受け入れ可能なサービス事業者との連絡調整をして、利用者の希望とズレがないか確認するところまでがこの作業の範囲です。
4. サービス担当者会議
原案を作成したら、続いてはそれをもとにサービス担当者会議がおこなわれます。サービス担当者会議とは、介護支援専門員を中心に利用者とそのご家族、介護サービス提供事業者の担当者、主治医などの関係者が集まっておこなう会議のことです。
プランの内容に問題はないかといった検討をおこなうのが目的で、決定したプランを定期的に見直す際にも開催されます。
5. ケアプランの原案を修正・再提案
サービス担当者会議で指摘された点や提案などの意見をもとに、必要な場合は原案を修正して再提案します。そして修正した原案を利用者とそのご家族に確認してもらい、同意を得るのがこの作業の流れです。
仮に修正点がなかったとしても、利用者とそのご家族に最終的な確認をしてもらい、同意を得ることが必要になります。
6. ケアプランの交付
原案を修正・再提案したら、あとはもう最終段階です。再提案したプランに問題がなければ、そのプランは最終決定となるため、利用者とそのご家族に計画書を交付・説明します。
ここで、同意を得られれば同意書に自署または記名・押印をもらうという流れです。なお、完成したケアプランは、介護サービス提供事業者への交付も必要となります。
7. モニタリング|ケアプランに沿ったサービスかを確認
作成における最終的な作業は、モニタリングです。モニタリングとは、プランに沿ったサービスが提供されているかどうかを確認することで、定期的に実施されます。モニタリングは、月1回以上利用者の自宅を訪問したり、サービス事業者に連絡をとったりすることでおこなわれるのが基本です。
ケアプランは6カ月程度で必ず見直しして、必要となれば再度アセスメントを実施してプランの修正と再交付をおこないます。
ケアプランの作成方法は?基本的な構成

ケアプランは、大きく3種類にわけられるため、受けるサービスなどによって構成が異なるのが特徴です。ここでは、一例として居宅サービスの構成をご紹介します。
居宅サービスのケアプランは、第1〜7表で構成されているものです。第1表と第2表が「居宅サービス計画書」で第3表が「週間サービス計画表」、第4表が「サービス担当者会議の要点」、第5表が「居宅介護支援経過」、第6表が「サービス利用票」、第7表が「サービス利用票別表」となります。
ケアプランを作成するときに注意したいポイント

利用者やそのご家族にとってよりよいケアプランを作成するためには、注意すべきポイントがあります。ここでは、ケアプランを作成する際に注意したいポイントを確認しておきましょう。
利用者とご家族の現状や要望がきちんと反映されているか
利用者やそのご家族の現状や要望が、プランにきちんと反映されているかどうかをしっかりと確認しましょう。
要望や困りごとなど、課題解決のための明確な目標の設定やサービスが計画されているかどうかが重要なポイントとなります。要望などをきちんと反映させるためには、聞きにくい情報なども最初にしっかり聞いておくことが大切です。
利用者やご家族にとって無理のないプランであるか
プランが利用者やそのご家族にとって無理のない内容であるかどうかも、作成時における注意すべきポイントです。
いくらそのプランの内容がよかったとしても、利用者やそのご家族にとって経済的・心理的に負担になってしまっては意味がありません。また、そのプランが継続可能かどうかもしっかり検討することが必要です。
作成したあとに定期的な見直しはされているか
ケアプランの作成は、プランを作成すれば終わりというわけではありません。定期的に見直しがされているかどうかも重要なポイントです。
利用者やそのご家族の健康や環境に変化が起こることは少なくありません。その都度確認してプランを見直すなど、柔軟に対応することが求められます。
介護職員がケアプランを作成するのに資格は必要ないが、介護支援専門員の資格保有で有利に

すでにご紹介したとおり、ケアプランの作成に資格は必要ないため、事業所に採用されればケアプランの作成を担当できる可能性はあります。
ただ、実際には介護支援専門員の資格保有を条件として求人を出されることが多いため、資格を保有しているほうが有利であることは間違いありません。介護職に就いて計画作成者になるなら、介護支援専門員の資格取得を目指すことをおすすめします。
引用元
厚生労働省:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の報酬・基準について(検討の方向性)
群馬県社会福祉協議会:介護予防サービス・支援計画書 作成ポイント
厚生労働省:介護サービス計画(ケアプラン)について
厚生労働省:「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正等について