【福祉現場のコロナ対策、どうしてますか?vol.2】 コミュニケーションの量と質を確保して、誰もが「安心して通える教室」に #2
未曾有のコロナ禍。感染対策に頭を悩ませている介護・福祉施設は少なくありません。そこで、実際に働く方々に対策事例をインタビュー。コロナ対策のヒントを探っていきます。
発達に特性のある子どもたちが通う「放課後等デイサービスわいわいプラス荒川教室」の教室長、竹澤久美子さん。昨春の緊急事態宣言以降、「普通」の感染対策が行えない状況でも、子どもたちがストレスを抱えないよう、その時できることを職員全員と話し合いながら乗り切ってきました。
今回は、長期化するコロナ禍において、家族や学校、職員との三位一体のコミュニケーションの強化や、コロナ対策補助金を使った新たな感染対策など、利用者も職員も安心できる施設運営についてお聞きします。
お話をうかがったのは…
放課後等デイサービス
わいわいプラス荒川教室
竹澤久美子さん
 短大で保育士の資格を取得。卒業後は子ども向けテーマパークでの勤務を経て、発達に特性がある子どもたちの療育支援を行う、東京都指定「放課後等デイサービスわいわいプラス荒川教室」の職員に。療育計画を立てる児童発達管理責任者の資格を取得するなど、療育指導員としてのキャリアを積む。現在7年目。
短大で保育士の資格を取得。卒業後は子ども向けテーマパークでの勤務を経て、発達に特性がある子どもたちの療育支援を行う、東京都指定「放課後等デイサービスわいわいプラス荒川教室」の職員に。療育計画を立てる児童発達管理責任者の資格を取得するなど、療育指導員としてのキャリアを積む。現在7年目。
「安心して通える教室」とは、保護者との信頼関係があってこそ

車内の密を回避するには乗車人数を減らす必要が。
東京都の補助金を使い、送迎車を一台増やして対応
──緊急事態宣言の解除後、多くのお子さんが利用を再開するにあたり、新たな対策は?
通常、学校へのお迎えやご自宅への送りは職員が車で行っています。よく、車内の飛沫防止として、座席の間をビニールシートで遮断する方法がありますよね? うちでは、子どもどうしがケンカをしたときに、職員がすぐに止めに入れないので使えないんです。そこで、都のコロナ対策補助金を使って車を一台、新たに購入。一台あたりの乗車人数を、これまでの7人から4人へ減らし、なるべく車内の密を回避するようにしました。
実際、保護者の方からも、送迎車の乗車人数については質問が多かったので、やってよかったなと思います。もちろん、マスク着用と窓開け換気もして、なるべく車内では大声で歌ったり話したりしないようにも伝えています。
──車以外に保護者の方から不安の声はありませんでしたか?
なかったですね。「安心して通わせられる教室」として信頼してもらうことがとにかく大事だと考えていて。そのためには情報共有が大切なので、受け渡し・引き渡しの時や連絡帳をとおして、今まで以上にお子さんの様子をしっかり伝えるようにしました。
連絡帳には、個々のお子さんの写真6枚を貼って、教室での様子をていねいに書き込んでいます。けっこう大変ですが、ここを怠ると保護者の方は不安になってしまうので、毎日、必死に書いてます(笑)。
対策をしながらでも「できること」を増やしていく
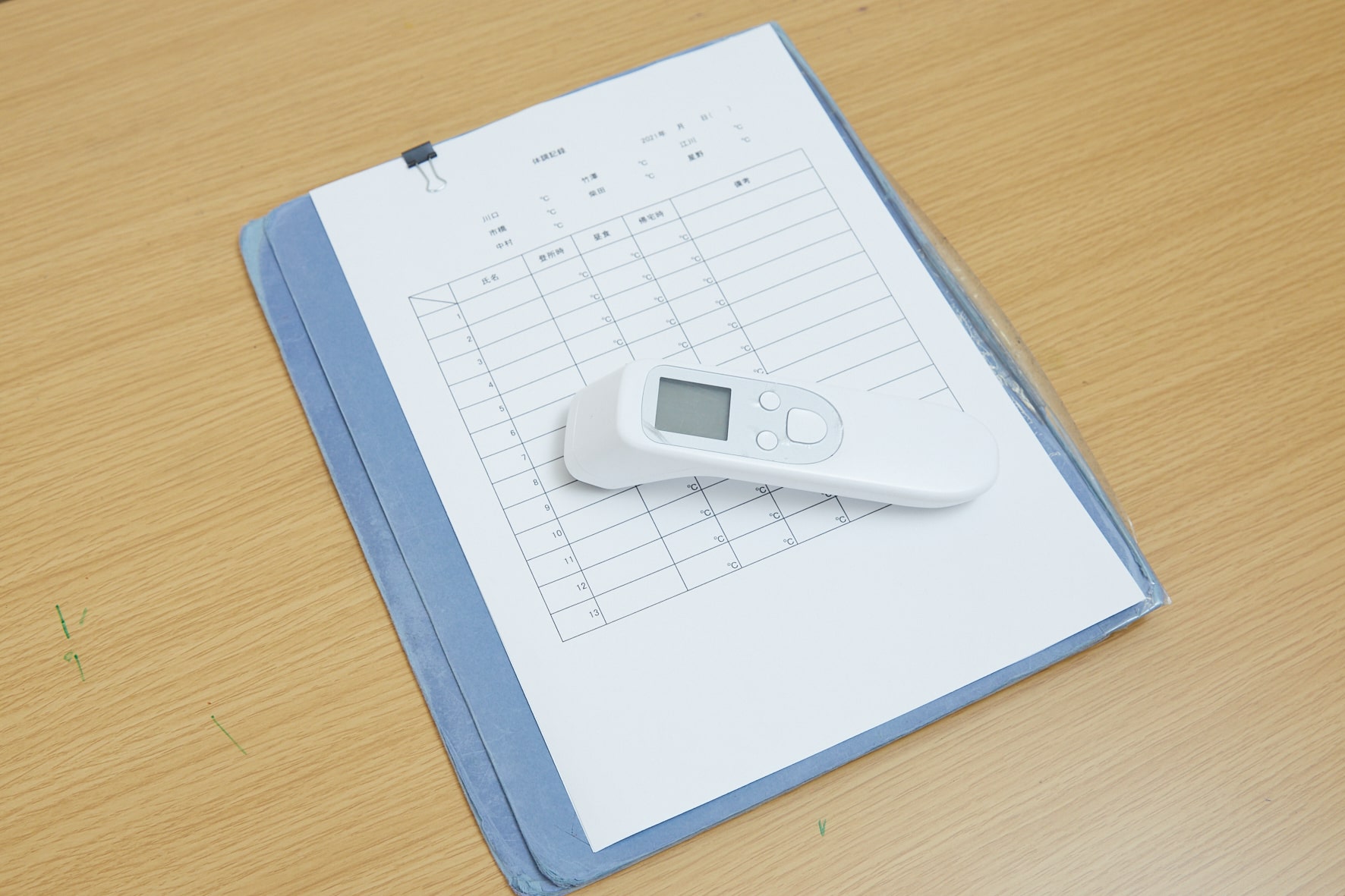
非接触型の体温計で子どもたちの検温をこまめに行い、体調を管理
──コロナ禍が長期化する中で、特に気をつけていることはありますか?
あとは検温の徹底ですね。重症化リスクの高い子どもたちが多いので、感染の兆候を逃さないよう、登室時、おやつの後、帰宅前とこまめに測っています。職員が学校に子どもを迎えに行く場合は、担当の先生に朝の検温結果や体調の変化を細かく聞いて、学校ともコミュニケーションをしっかり取るようにしています。
──コロナ禍でできないことが多くなるなか、療育の質はどう保っていますか?
当初は近所の公園さえ遊べなくなってしまいましたが、現在は教室内でできる運動をしたり、走り回れる広場で体を動かしたり、基本的な療育内容はコロナ前と特に変わりなく行うことができています。
ただ、ちょっと遠方への外出を自粛しなければならないのが痛いですね。今までは、博物館や動物園など、発達に特性のある子を連れてご家族だけでは行きにくい場所へ、定期的に出かけていました。それが、コロナ禍ですべて中止に。また、同じ系列の足立教室と行っていた交流イベントも中止。子供たちが経験を積むためのさまざまな機会がなくなってしまいました。
──子どもたちの楽しみがなくなったままなのですね。
初期のころは、子どもたちも「コロナだからしょうがない」と納得していたのですが、さすがにここまで続くとそれも難しくて…。代わりに、感染対策にしっかり気をつけながら調理実習の回数を増やすなどして、楽しめる企画を少しずつ取り入れています。
いつまでも「できない」ままにしないで、コロナ禍でも「できること」を増やしていこうと、職員といろいろ考えているところです。
支援内容に差がでないよう、情報のトップダウンは明確に

「慣れによる気持ちのゆるみが一番怖い」と語る竹澤さん
──職員の側も、長期化とともに危機意識が薄れてきませんか?
それが一番怖いですね。感染対策は職員全員が徹底してこそ効果が発揮されるものなので、私のほうできちんと目を配るようにしています。ただ、職員全員、この教室に通う子どもたちにとって感染は命に直結することだと重く受け止めていて、時間がたっても「なあなあ」にならいのは心強いですね。
──勤務はシフト制とのことですが、職員の方々とはどのようにコミュニケーションを取っていますか?
毎日、朝夕2回のミーティングに加え、月に1回の教室ミーティングをとおして、支援内容の確認を細かく行っています。
あとは、気になったらすぐ個別に会話をするよう心がけていますね。人によって教え方が違うと、支援内容そのものが変わってしまうこともあるので。とくにコロナ感染対策の場合、子どもたちも何が正しいのか分からなくなってしまったり、「この先生ならさぼってもいいか」と怠けてしまったり、混乱を招くことになりかねないので。
──この一年、コロナ対策と業務を両立してきたことで、学んだことはありますか?
感染状況がつねに変化するなか、とくに大事だなと感じたのが、情報の選び方、伝え方です。みんなが見えない不安に戸惑っていた初期から、感染が急速に拡大した不時期、この状況にやや慣れてしまった時期。いずれの時期においても、本当にさまざまな情報が耳に入ってきます。教室長である私が情報に流されて右往左往すると、教室全体の方針が揺らいでしまうので、情報をきちんと精査する重要性は強く感じましたね。
小規模施設だからこそチーム力の強化が鍵になると感じています
──コロナ対策はしばらく続くことが予想されます。
小規模施設のため、もともと職員どうしで助け合って働いてきました。ところがこの一年、先が見通せないコロナ禍に置かれたことで、みんなで協力する場面がさらに増えて。あらためて、チーム力の重要性を認識しています。私だけが頑張っても、おそらく空回りしてうまくいかなかったはず。今後も、職員のみんなと量、質ともにしっかりとコミュニケーションを取りながら、子どもたちが安心かつ楽しく通える教室運営を目指していきたいですね。
コロナと向き合いながら働く「放課後等デイサービス わいわいプラス」ならではの取り組み
1. 利用者と職員、双方が安心できる施設運営
2. 情報を精査し運営内容の質を下げない
3. 目の前の対策を怠らない堅実なチーム力
対応の難しい状況が続く中でも、当たり前のことを怠らず、少しずつ「できること」を増やしていく。その積み重ねが、利用者からの信頼につながっていることが分かりました。竹澤さんのコロナ禍のお仕事、ぜひ参考にしてください。
▽前編はこちら▽
【福祉現場のコロナ対策、どうしてますか?vol.2】「普通」の対策ができないことも。療育現場のリアル #1>>
取材・文/池田 泉
撮影/柴田大地(fort)

















