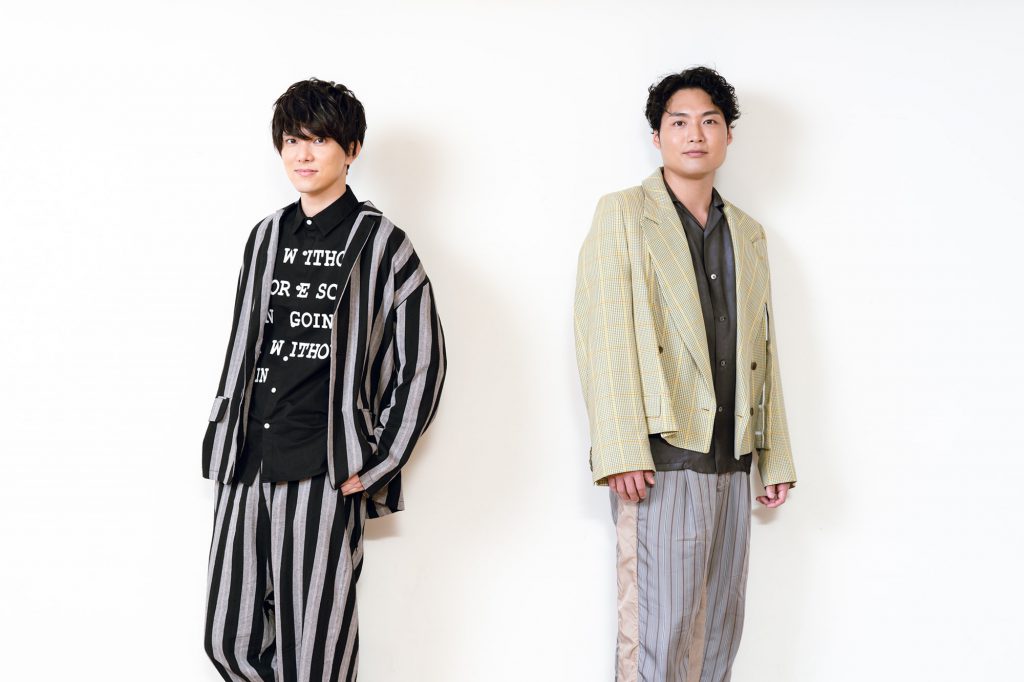社会福祉士の倫理綱領(りんりこうりょう)とは?内容をわかりやすく解説
社会福祉士は、社会福祉の分野においてエキスパートといえる存在です。人々を病気や障害・貧困などから守り、専門的知識や技術によってサポートする社会的に重要な役割を担っています。
実際に社会福祉士として働くうえで重要となるのが、倫理綱領(りんりこうりょう)です。そこにはどのような内容が書かれているのか、倫理綱領制定の経緯や重要性も含めてご紹介していきましょう。
倫理綱領とは社会福祉士の行動指針

倫理綱領は、社会福祉士が職務を遂行するうえでの行動指針を示したものです。専門職として責任を果たすために欠かせない内容が盛り込まれており、利用者をサポートするうえでも、倫理綱領にもとづく対応が求められます。
倫理綱領にはどんなことが書かれているの?
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」は、1995年に日本社会福祉士会によって採択されました。その後、急速なグローバル化や経済・金融・情報・環境などの変化にともない、人々の生活課題が多様化しています。これを踏まえ、2020年6月に改訂・採択し直されたものが、現在の社会福祉士の倫理綱領です。
「もし社会福祉士として働くうえで、倫理綱領がなかったら」と、想像してみてください。専門職でありながら、自ら行う行為に関する指針がなければ、質の高いサービスの提供には結びつかないばかりか、モラルを保てません。社会福祉士の仕事が成り立たなくなることさえ考えられます。
価値観の多様化にともない、個々の利用者に合わせた細やかなサポートが必要な現在だからこそ、社会福祉士が働くうえで、倫理綱領の内容を理解する重要性が増してきています。
倫理綱領にはどんなことが書かれているの?

倫理綱領には、具体的にどのようなことが書かれているのでしょうか。ここでは、ポイントを押さえて紹介します。
前文
倫理綱領の前文では、社会福祉士は「人々がつながりを実感できる社会変革と社会的包摂の実現を目指す専門職」であると、定義されています。
社会的包摂とは、誰も排除されることなく、全員が社会に参画する機会を持てる状態のことです。社会福祉士は支援を必要とする人々の孤立を防ぎ、社会とのつながりを促進する役割を担っています。
また、前文のなかで重要なポイントが「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」への理解です。これは社会福祉の国際的な基本理念を示し、「エンパワメント」や「人権・多様性の尊重」などの事項が含まれています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
エンパワメントとは、ハンディキャップやマイナス面に着目して援助をするのではなく、長所に着目し、本来の力や可能性を引き出そうとする援助の方法です。これにもとづき社会福祉士は利用者の価値観を尊重し、自立をうながす姿勢が求められます。
前文は倫理綱領の基本になる内容がまとめられているため、しっかり理解するようにしましょう。
6つの原理
社会福祉士が業務に取り組むうえで指針となる価値観をまとめた「倫理綱領の原理」は、以下の6つの概念で構成されています。
・人間の尊厳
・人権
・社会正義
・集団的責任
・多様性の尊重
・全人的存在
ここではそれぞれの原理について、わかりやすく解説します。
1.人間の尊厳
人間の尊厳とは「すべての人をかけがえのない存在」として尊重する考え方のことです。
倫理綱領には「ソーシャルワーカーは、すべての人々を、出自、人種、民族、国籍、性別、性自認、性的指向、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況などの違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。」と記載されています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
つまり社会福祉士は、利用者の生き方・考え方を尊重しながら支援を行う姿勢が求められます。個々の価値観に寄り添い、自己決定できる環境を整えることが重要なのです。
2.人権
人権とは、すべての人間が生まれながらにして持つ、侵してはならない権利のことです。
倫理綱領には「ソーシャルワーカーは、すべての人々を生まれながらにして侵すことのできない権利を有する存在であることを認識し、いかなる理由によってもその権利の抑圧・侵害・略奪を容認しない。」と記載されています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
どのような状況にあっても、他者の人権が抑圧されたり侵害されたりする状況を容認しない姿勢が、社会福祉士に求められます。
3.社会正義
社会正義とは、社会の人々が平等に扱われ、社会全体の福祉の保障と秩序が維持されるために必要な判断基準のことです。
倫理綱領には「ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。」と記載されています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
ポイントとして、2020年の倫理綱領改定では「無関心」が社会正義を損なう要因として追加されました。不正や不平などを見過ごすことなく、積極的に関与する姿勢が社会福祉士には求められます。
4.集団的責任
集団的責任とは、人間関係における相互扶助や環境への配慮など集団が持つ責任のことで、2020年の改定で、新たに倫理綱領に追加されました。
倫理綱領には「ソーシャルワーカーは、集団の有する力と責任を認識し、人と環境の双方に働きかけて、互恵的な社会の実現に貢献する。」と記載されています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
社会全体が助け合えるように集団の持つ力と責任を理解し、個人だけでなく、その人の属する環境にも働きかけることが、社会福祉士の役割です。
5.多様性の尊重
多様性の尊重とは、偏った価値観で他者を判断せず、個々の存在や考え方を大切にすることです。
倫理綱領には、「ソーシャルワーカーは、個人、家族、集団、地域社会に存在する多様性を認識し、それらを尊重する社会の実現をめざす。」と記載されています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
これにもとづき社会福祉士は、利用者ひとりひとりの価値観や生き方を尊重しながら支援を行う姿勢が求められます。固定観念にとらわれず、多様な視点を受け入れる意識が大切です。
6.全人的存在
全人的存在とは、人を多角的にとらえる考え方です。
倫理綱領には「ソーシャルワーカーは、すべての人々を生物的、心理的、社会的、文化的、スピリチュアルな側面からなる全人的な存在として認識する。」と記載されています。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
社会福祉士は利用者を全人的な存在として捉え、相手の抱える痛みに寄り添い、状況に適した柔軟な支援を提供する役割を求められます。
一言に痛みといっても、「身体的な痛み(病気・ケガ)」のみならず、「精神的な痛み(ストレス・不安)」「社会的な痛み(貧困・差別)」「スピリチュアルな痛み(生きる意味の喪失)」などが存在します。
社会福祉士は利用者の抱えるさまざまな痛みに向き合い、最適なケアを提供する責務を負っているのです。
4つの倫理基準
倫理基準とは、6つの原理を行動に落とし込むための具体的な行動指針のことです。具体的には以下の4つが定められています。
・クライエントに対する倫理責任
・組織・職場に対する倫理責任
・社会に対する倫理責任
・専門職としての倫理責任
ここでは、それぞれの項目をわかりやすく解説します。
1.クライエントに対する倫理責任
利用者に対する倫理責任として定められている行動指針は、以下の12項目です。
・クライエントとの関係
・クライエントの利益の最優先
・受容
・説明責任
・クライエントの自己決定の尊重
・参加の促進
・クライエントの意思決定への対応
・プライバシーの尊重と秘密の保持
・記録の開示
・差別や虐待の禁止
・権利擁護
・情報処理技術の適切な使用
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
多忙な業務をこなしていると、考え方やケアの内容が自分本位に傾いてしまいがちです。しかし、あくまでも利用者の利益を最優先に考えるという、基本に立ち返る心がけが重要です。
たとえば利用者がスムーズに自己決定できるような説明を行ったり、個人情報は厳重に管理し、プライバシーが侵害されないよう配慮したりしなければなりません。
また介護・福祉の現場においても性的差別や虐待といった内容が問題となっており、これらの行為を禁止する項目も定められています。
2.組織・職場に対する倫理責任
実践現場における倫理責任には、以下の6項目が定められています。
・最良の実践を行う責務
・同僚などへの敬意
・倫理綱領の理解の促進
・倫理的実践の推進
・組織内アドボカシーの促進
・組織改革
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
自分の持つ専門的な知識や技術は業務に惜しみなく生かすことのほか、他職種と連携しながらサービス提供を行うことなどが盛り込まれています。
しかし、倫理上の内容と現場の状況の間に、ジレンマが生じることもあるでしょう。このような場合、本綱領の原則を尊重し遵守できるような働きかけが必要であると規定されています。
社会福祉士として働きながら、当たり前のように行っている業務を点検し再評価することで、よりよい方向にうながす姿勢が重要です。
なお、アドボカシーとは個人が本来持っている権利を、さまざまな理由により行使できない人を支援する仕組みを指します。
3.社会に対する倫理責任
社会に対する倫理責任では、「ソーシャル・インクルージョン」や「社会の働きかけ」「グローバル社会への働きかけ」について定められています。
ソーシャル・インクルージョンとは、社会的包摂とも訳される言葉です。あらゆる差別や貧困・抑圧・排除・暴力・環境破壊などから守ることを意味しています。
福祉は国内だけの問題にとどまらず、専門職との連携による社会への働きかけのほか、国際的問題解決に向けて、全世界のソーシャルワーカーと連携することについても定義されています。
4.専門職としての倫理責任
専門職としての倫理責任として定められている行動の指針は、以下の8項目です。
・専門性の向上
・専門職の啓発
・信用失墜行為の禁止
・社会的信用の保持
・専門職の擁護
・教育・訓練・管理における責務
・調査・研究
・自己管理
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領
社会福祉士は国家資格であり、社会的信用の高い専門職であるということを自覚しなければなりません。信用を失墜するような行為を行わないことはもちろん、教育や訓練によって専門性を向上させることも盛り込まれているのが特徴です。
ソーシャルワーカーが不当な批判を受けるような事態が起これば、専門職と連携を図りながら立場を擁護することについても記されています。
倫理綱領を理解して社会福祉士としての行動指針を明確にしよう

社会福祉士の倫理綱領は仕事の定義や利用者、実践現場や社会に対する倫理的責任や行動指針についてまとめられたものであり、ソーシャルワーカーとして働くうえでなくてはならないものです。
しかし、介護や福祉の現場では、倫理綱領と実際に起こっている事象との間にジレンマを抱えることもあるでしょう。
社会福祉士としてあるべき姿と現実とのギャップに悩んでしまうこともあるかもしれません。
リジョブケアでは、社会福祉士向けの求人が多数そろっています。倫理綱領の考え方に沿ってやりがいを感じながら働ける、あなたにピッタリの職場が見つかるかもしれません。ぜひ一度、気になる求人がないかチェックしてみましょう。
引用元
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会:倫理綱領