【今さら聞けない!? 介護のお仕事の基本vol.27】利用者が急変! まずは何をすればいい?
介護現場で起こりがちな困りごとへの対処法をご紹介する当企画。今回は、利用者が急変したときの対処について取り上げます。学習したことがあっても、いざその場に直面すると動転してしまうのも。こういった機会に復習しておくと慌てずに対応できるようになりますよ。
利用者・入所者の急変に居合わせてしまった! 救命処置ってどうするの?

「急変」とは、心停止、呼吸停止、ショック状態、意識障害と、これらに準ずる重篤な状態のこと。終末期の段階にあるなど、利用者・入所者の状況によっては死に向かう自然の経過としてある程度予測がつきます。しかしそうでない場合は、介護職であっても気が動転してしまう人もいるでしょう。
ですが、基本的な救命処置は、介護職はもちろん、一般の人でもできることです。いざという時に慌てないためにも、処置の基本をおさらいしておきましょう。
「急変」に遭遇したら最初にやるべきことは、次の2つです。
・反応の確認
・意識レベルのチェック
今回は、この2つについて、詳しくご紹介します。
ポイント1:まずは名前を呼び、反応の有無を確認
まずは、肩をたたきながら、耳元ではっきりと名前を呼びかけましょう。呼びかけに対して返事をしたり、うなずいたり、目を開けたりなど、応えようとする仕草があれば「反応あり」と判断します。これらの仕草がみられなかった場合は、左右の手を軽く握り、「聞こえていたら手を握ってください」と声をかけてみましょう。これで握り返せたら「反応あり」です。
ポイント2:「反応なし」の場合、痛み刺激で意識レベルチェックを
全く反応がないようにみえる場合でも、痛み刺激に対しては反応がみられる場合があります。痛み刺激の与え方は、胸骨を指の関節で押す、手の甲を軽くつねるといった方法が一般的です。この反応の違いで意識レベルを判断することができます。
・払いのける動きをする → 意識レベル100
・手足が動く、顔をしかめる → 意識レベル200
・全く反応しない → 意識レベル300
救急隊や医療専門職に引き継ぐ際に伝えられると、適切な診断や治療に結びつくので覚えておくとよいでしょう。
反応の確認後にとるべき2つの行動
1.反応あり → 応援を呼び、回復体位にして様子を見守る
2.反応なし → 応援を呼び、AEDと救急車を手配し、気道確保
予期せぬ「急変」に遭遇したら、慌てずに落ち着いて対応することが大切です。応急処置や救命処置、バイタルサインのチェック、他の利用者・入所者への対応など、やることはたくさん。反応確認をしたらすぐに応援を呼び、スタッフで協力して対応しましょう。
救急車を呼ぶべきか判断に迷ったら、「#7119 救急安心センター」に電話を。医師や看護師、相談員が状況に合わせた対応を案内してくれます。自治体によって導入されていないところや、番号が違うことがあるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
文:細川光恵
参考:「介護現場で使える 急変時対応便利帖」株式会社翔泳社
監修
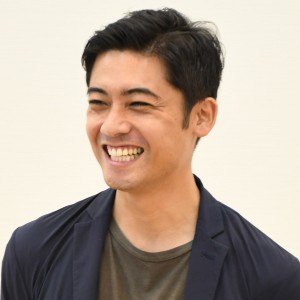
中浜 崇之さん
介護ラボしゅう 代表/株式会社Salud代表取締役/NPO法人 Ubdobe(医療福祉エンターテイメント) 理事/株式会社介護コネクション 執行役
1983年東京生まれ。ヘルパー2級を取得後、アルバイト先の特別養護老人ホームにて正規職員へ。約10年、特別養護老人ホームとデイサービスで勤務。その後、デイサービスや入居施設などの立ち上げから携わる。現在は、介護現場で勤務しながらNPO法人Ubdobe理事、株式会社介護コネクション執行役なども務める。2010年に「介護を文化へ」をテーマに『介護ラボしゅう』を立ち上げ、毎月の定例勉強会などを通じて、介護事業者のネットワーク作りに尽力している。
















