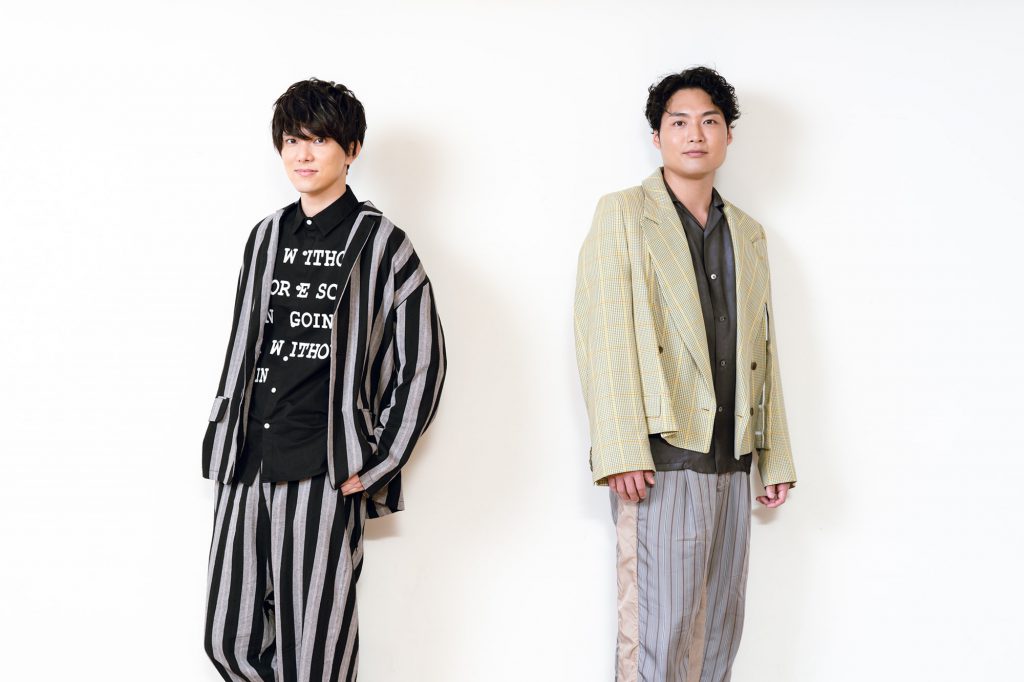社会福祉士の一般養成施設とは?費用相場や自分に合う施設を選ぶポイントを解説
社会福祉士の受験資格を取得するためには約11とおりの方法があり、その選択肢のなかに、「一般養成施設」に通って受験資格を得るルートがあります。この一般養成施設とはいったいどのような施設なのでしょうか。
今回は、社会福祉士の受験資格を取得するルートである一般養成施設について詳しくご紹介します。
- 一般養成施設ではどんなことを学ぶの?カリキュラムを紹介
- 一般養成施設ではどんなことを学ぶの?カリキュラムを紹介
- どう選ぶ?自分に合った養成施設を選ぶポイントを紹介
- 1.学習方法で選ぶ|通信課程+スクーリング・通学
- 2.費用で選ぶ|通学と通信で大きく異なる
- 自宅からのアクセスの良さ|通信でもスクーリングがある
- 4.合格実績をチェック|試験対策の充実度に影響している場合がある
- 【通学・通信】おすすめの一般養成施設を紹介!
- 東京福祉専門学校|社会福祉士一般養成科【通学1年・通信1年6カ月】
- 日本福祉教育専門学校|社会福祉士養成学科【通学(昼間・夜間)1年・通信1年6カ月】
- 資格の大原|社会福祉士養成コース【通学(夜間)1年・通信1年6カ月】
- 社会福祉士国家試験の試験概要
- 社会福祉士国家試験の勉強方法のコツ3選
- 受験資格を満たして国家試験に臨もう!
一般養成施設ではどんなことを学ぶの?カリキュラムを紹介

社会福祉士の受験資格を一般養成施設で得る必要があるのは、どのような人なのでしょうか。ここでは、社会福祉士の受験資格が取得できる一般養成施設とは、どんな施設なのかを詳しくご紹介します。
社会福祉士国家試験の受験資格を得る養成施設のひとつ
一般養成施設とは、福祉系大学以外の4年制大学を卒業した人や、指定施設などで相談援助実務を4年以上経験された人が入学対象者となる施設のこと。修学年数は1年以上で、近年は通学だけでなく通信課程で学ぶことも可能です。
似たような名称で混同されやすい施設に、短期養成施設があります。短期養成施設とは6カ月以上修学する施設のことで、まず通学期間が異なります。通学の対象者も、福祉系大学・短大に進学し、厚生労働省が指定する基礎科目を履修した人です。
短期養成施設は基本的に通信で学ぶことになり、通学はほとんどありません。
関連記事
社会福祉士の養成施設とは?一般養成施設と短期養成施設の違いを解説!
一般養成施設での勉強を必要とするルートとは
ここからは具体的に社会福祉士の受験資格を得るために、一般養成施設で学ばなければならない人を詳しくご紹介します。ご自身が対象になるのかどうかをチェックしてみましょう。
引用元
社会福祉振興・試験センター:【社会福祉士国家試験】受験資格|資格取得ルート図
一般大学・短大ルート|4年制大学・2年~3年短大卒業
一般養成施設の入学対象者は一般大学4年・一般短期大学3年・一般短期大学2年のいずれかを卒業した人です。ただし、すべての人が一般養成施設で学べば、すぐに社会福祉士の受験資格を得られるわけではありません。
一般短期大学3年・一般短期大学2年を卒業した人の場合は、一般養成施設に入る前に相談業務に従事して、実務経験を積む必要があります。この実務経験を積む年数も卒業した大学によって異なり、一般短期大学3年を卒業した人は1年、一般短期大学2年を卒業した人は2年の実務経験が必要です。
引用元
社会福祉振興・試験センター:【社会福祉士国家試験】受験資格|一般大学等
相談援助業務ルート|実務経験4年以上
大学などで学んでいなくても、一般養成施設で学んだあとに社会福祉士の受験資格を取れるルートがあります。それは第11号というルートです。
このルートは最終学歴に関係なく、相談援助業務を4年間行うことで、一般養成施設へ入ることができ、社会福祉士の受験資格を得られるルートです。最終学歴が大学や短期大学以外である方は、このルートで社会福祉士の受験資格を得られます。
引用元
社会福祉振興・試験センター:【社会福祉士国家試験】受験資格|相談援助業務(実務経験)
一般養成施設ではどんなことを学ぶの?カリキュラムを紹介

一般養成施設は、ほかの社会福祉士の受験資格を得るためのルートに比べて、学習期間が比較的長いのが特徴です。ここでは、一般養成施設ではどんなことを学ぶのかをご紹介します。
座学|社会福祉士に必要な基礎・専門知識を学ぶ
座学では、基礎的な教養を身につけていきます。毎月3科目程度の課題を履修し、レポートを提出することが必要です。履修科目は共通科目と専門科目の2種類で構成されており、人体の解剖生理から心理学・社会福祉学など多岐にわたります。
実習|実務経験が足りない人は実習を受講
実習は一般養成施設に通うすべての人が対象ではなく、実務経験が足りない人のみが対象です。具体的に実習が必要となるのは、厚生労働省が定める施設での就労期間が1年未満の人で、実習時間は180時間(23日間以上)。
おおむね一般養成施設が契約している施設が実習先になります。
関連記事
社会福祉士の実習について解説!どんな場合に実習免除になるの?
国家試験対策|合格を目指したサポートも
社会福祉士になるためには、最終的に国家試験に合格しなければなりません。一般養成施設では、国家試験のサポート体制も充実しており、施設によってもサポート内容が異なる場合もあります。
専任講師を常駐させて疑問をすぐに解消できるように環境を整えたり、個別対策をしたりと、短期間の学びで合格できるように内容が充実している施設もあります。
どう選ぶ?自分に合った養成施設を選ぶポイントを紹介

さまざまな一般養成施設があり、選択肢は豊富ですが、なによりも大切なのは自分に合った養成施設かどうかというところ。自分に合った一般養成施設であれば学習もはかどり、国家試験への合格も見えてくるかもしれません。
ここからは、自分に合った養成施設の選び方のポイントをご紹介します。
1.学習方法で選ぶ|通信課程+スクーリング・通学
一般養成施設での養成課程には、通学タイプと通信タイプがあります。通学の場合は、期間が1年間であり、昼の部と夜の部で展開されています。
仕事をしながら一般養成施設に通うのであれば夜の部、家庭と両立するのであれば昼の部といった具合に、自分の生活スタイルに合わせて通える点が特徴です。
通信の場合は、1年6カ月の受講が必要となり、通学よりも期間は長くなります。通信だから一度も施設に行かなくてよいということではなく、スクーリングと呼ばれる通学の機会が何度かあります。
通信は、月ごとの課題で自ら知識を深めなければなりませんが、課題レポートの提出で履修できるので、働きながら自分のペースで学びやすい方法といえるでしょう。
2.費用で選ぶ|通学と通信で大きく異なる
一般養成施設にかかる学費は、施設や通学方法によって異なります。以下は目安となる費用の相場です。
| 通学方法 | 費用相場 |
| 昼間通学 | 100万円 |
| 夜間通学 | 40~60万円 |
| 通信制 | 30~50万円 |
一般的に通信課程のほうが費用は抑えられる傾向にあります。理由としては、施設への設備費などを負担しなくてよいことや、講師から直接講義を受けるわけではないので、授業料も抑えられる点が挙げられます。
とはいえ、通信課程の場合は課題の郵送料や、インターネットを接続するための通信費や光熱費がかかります。実習が必要な場合、通信であっても通学よりも費用がかさむ可能性もあるかもしれません。
自分の受けるカリキュラムを確認しつつ、費用で一般養成施設を選ぶのもよいでしょう。
自宅からのアクセスの良さ|通信でもスクーリングがある
通信課程を選んだとしても、スクーリングのために通学しなければならないこともあります。通信だからどこの一般養成施設でもよいと考えず、通学することも念頭において自宅から通いやすいところを選びましょう。
もし仕事のあとに職場から直接通うならば、職場から近い一般養成施設を選ぶのもよいでしょう。通学にも費用がかかるので、自宅から近い一般養成施設を選ぶと経済的です。
独立行政法人「福祉医療機構」のWebサイトでは、全国の一般養成施設を一覧で確認できるため、自宅から通える施設を探してみましょう。
引用元
独立行政法人福祉医療機構:社会福祉士一般養成施設一覧
4.合格実績をチェック|試験対策の充実度に影響している場合がある
自宅から通える一般養成施設が複数ある場合は、合格実績で比較するのも有効です。社会福祉士試験の受験資格は、どの施設を卒業しても得られますが、試験対策の充実度は施設ごとに異なります。その違いが合格率に反映されることも少なくありません。
合格実績が高い施設ほど、国家試験対策が充実している可能性は高いと考えられます。各施設のホームページには、過去の合格率が掲載されているため、施設名で検索して確認するとよいでしょう。
近年の社会福祉士国家試験の合格率を紹介
社会福祉士国家試験の合格率は、年度ごとに変動があります。よってスクールのホームページに記載されている合格率が、いつの実績であるかを確認することが大切です。
以下は近年の合格率の推移です。
| 回次 | 実施年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 第37回 | 令和6年度 | 27,616 | 15,561 | 56.3 |
| 第36回 | 令和5年度 | 34,539 | 20,050 | 58.1 |
| 第35回 | 令和4年度 | 36,974 | 16,338 | 44.2 |
| 第34回 | 令和3年度 | 34,563 | 10,742 | 31.1 |
| 第33回 | 令和2年度 | 35,287 | 10,333 | 29.3 |
| 第32回 | 令和元年度 | 39,629 | 11,612 | 29.3 |
第35回試験以降の合格率の上昇の背景には、基本的な知識を問う問題が出題されるように、内容の見直しがなされたことが推測されます。
全体の合格率は年度によって異なる状況のため、ホームページに掲載されている合格率がどの年度のデータかを確認してから、実績が高いか低いか判断するとよいでしょう。
引用元
厚生労働省:社会福祉士国家試験の受験者・合格者の推移
【通学・通信】おすすめの一般養成施設を紹介!

一般養成施設は施設数も豊富なので、どの施設を選べばいいか悩んでしまうかもしれません。ここでは、通信・通学におすすめしたい一般養成施設をご紹介します。
東京福祉専門学校|社会福祉士一般養成科【通学1年・通信1年6カ月】
昼の部の通学と通信課程という選択肢があり、即戦力として働く社会福祉士の養成を目標としている施設です。とくに力を入れているのが国家試験対策。通学では伴走型の国家試験対策を取り入れ、専任教員がそれぞれの受講者に最適な国家試験対策をプランニングしてくれます。
通信においては、課題が国家試験の出題形式に則したものとなっているので、課題に取り組みながら国家試験対策もできる点が魅力です。課題はパソコン・タブレット・スマホでアクセスでき、いつでもどこでも学べる体制が整えられています。
引用元
東京福祉専門学校
東京福祉専門学校:社会福祉士一般養成科
東京福祉専門学校:社会福祉士通信課程
日本福祉教育専門学校|社会福祉士養成学科【通学(昼間・夜間)1年・通信1年6カ月】
日本福祉教育専門学校は、受講者のライフスタイルに合わせて複数のコースが用意された、一般養成施設です。
昼間部の授業は16:10に終了するため、私生活と両立しやすい面があります。実習も、春休みや夏休みといった長期休みの期間に実施されており、参加しやすいのが特徴です。
夜間部には2コースあり、月~土曜日に集中して学ぶナイトコースと、週休2日制で学べるトワイライトコースが設けられています。通信過程も用意されており、忙しく働いていて通学が難しい方でも学習に取り組めます。
同校の魅力は高い国家試験合格率です。令和6年度に発表された第37回社会福祉士国家試験の合格率は56.329.3%です。
一方、同校の第37回社会福祉士国家試験の合格率は以下のとおりです。
昼間部:97.3%
夜間部(トワイライトコース):100.0%
夜間部(ナイトコース):100.0%
通信過程:81.7%
このように全国平均と比較して高い合格率を記録しており、施設における国家試験の対策が目に見える結果として表れています。通信にも通学して学べる国家試験の特別対策講座も複数用意されており、集中して国家試験の準備ができる環境が整っている点も魅力です。
引用元
日本福祉教育専門学校
日本福祉教育専門学校:国家試験合格率の高さ
日本福祉教育専門学校:社会福祉士養成学科通学部(昼間部)・1年制
日本福祉教育専門学校:社会福祉士養成科通学部(夜間部)トワイライトコース・ナイトコース1年制
日本福祉教育専門学校:社会福祉士養成通信課程
資格の大原|社会福祉士養成コース【通学(夜間)1年・通信1年6カ月】
ほかの一般養成施設と同様に国家試験対策には力をいれており、通学は過去3年間合格率90%以上を記録しています。
通信の場合、合格率が通学よりも低い傾向にありますが、大原では通信においても7割以上の合格率を記録。オリジナルの問題集やDVD教材・担当講師と国家試験直前までメールや電話でやり取りができるなど、通信でも国家試験に合格しやすい環境が整っています。
通学は夜間部のみ。働きながら国家試験合格が目指せるように、学習面以外の点もサポート。実習先の配慮や、現在無職の学生のために社会福祉士の仕事が学べるアルバイト先の紹介など、サポートが充実しています。
社会福祉士国家試験の試験概要

社会福祉士国家試験の準備を適切に行うため、まずは試験の概要を知ることが大切です。ここでは試験のスケジュール・試験科目・合格基準などを紹介します。
試験のスケジュール
社会福祉士国家試験は毎年2月上旬に実施されるため、この時期に照準を合わせて学習計画を立てることが重要です。また受験申し込みの期間は例年9月上旬から10月上旬の期間に設定されており、期限をすぎると受験できません。忘れずに申し込むようにしましょう。
試験科目
社会福祉士国家試験は、19科目にわたる幅広い分野から出題されます。試験は午前・午後の2部構成で実施され、知識の総合力が求められます。
以下に、第37回試験の科目を紹介します。
| 試験日 | 令和7年2月2日(日曜日)午前 | 令和7年2月2日(日曜日)午後 |
| 試験科目 | ①医学概論
②心理学と心理的支援 ③社会学と社会システム ④社会福祉の原理と政策 ⑤社会保障 ⑥権利擁護を支える法制度 ⑦地域福祉と包括的支援体制 ⑧障害者福祉 ⑨刑事司法と福祉 ⑩ソーシャルワークの基盤と専門職 ⑪ソーシャルワークの理論と方法 ⑫社会福祉調査の基礎 |
⑬高齢者福祉
⑭児童・家庭福祉 ⑮貧困に対する支援 ⑯保健医療と福祉 ⑰ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) ⑱ソーシャルワークの理論と方法(専門) ⑲福祉サービスの組織と経営 |
試験は、社会福祉の基礎知識から専門的なソーシャルワーク理論・法律・福祉政策にいたるまで多岐にわたります。過去問に取り組み、各科目の出題傾向を理解することが合格をつかむための鍵です。
引用元
社会福祉振興・試験センター:【社会福祉士国家試験】試験概要
合格基準
社会福祉士国家試験の合格基準は、総得点の約60%以上とされています。ただし、合格には6つの科目群すべてで、1点以上の得点を獲得することが求められます。
前述のとおり、試験科目は19科目にわかれていますが、科目群は以下の6つです。
1.医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム
2.社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度
3.地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉
4.ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎
5.高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援、保健医療と福祉
6.ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、福祉サービスの組織と経営
どれか1つでも0点の科目群があると、ほかの科目群で高得点を取っていても不合格となります。合格基準が厳しく設定されているため、バランスの取れた学習が必要です。一般養成施設では試験対策のサポートを受けられますが、自分でも正しい学習方法を理解し、計画的に取り組んでいきましょう。
引用元
社会福祉振興・試験センター:【社会福祉士国家試験】合格基準
社会福祉士国家試験の勉強方法のコツ3選

ここでは社会福祉士国家試験に合格するために、意識するとよい勉強方法のコツを3つ紹介します。
1.事前に学習スケジュールを立てる
試験対策は計画的に進めることが重要です。試験日から逆算し、無理のない学習スケジュールを立てることで、効率的に知識を定着させられます。
社会福祉士国家試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に300時間程度とされています。仕事や学業と両立する場合、残りの日数を計算し、平日・休日の学習時間を設定するとよいでしょう。また、自分で計画を立てるのが難しい場合は、一般養成施設の講師に相談するのも一つの方法です。
2.最新の過去問を解く
合格の確率を高めるには、実際の試験問題に慣れることが重要です。過去問を解くことで、出題傾向の把握・苦手分野の発見・時間配分のシミュレーションを行えます。これにより、試験本番で落ち着いて取り組めるようになります。
注意点として、過去問を使用する際は最新のものを選ぶようにしましょう。古い過去問は、法改正や試験制度の変更に対応しておらず、解説の内容に古い情報が含まれているケースがあります。過去問やテキストには、タイトルに何年度のものかが記載されているため、確認してから購入しましょう。
3.苦手科目の復習をしっかり行う
社会福祉士国家試験では、すべての科目群で1点以上の得点を取る必要があります。そのため、苦手科目を放置せず、確実に得点できるよう復習を徹底することが重要です。
過去問に取り組むなかで、わからなかった問題には印をつけ、繰り返し解きながら知識を定着させましょう。苦手科目を減らしていくことで、合格できる可能性を高められます。
受験資格を満たして国家試験に臨もう!

通学・通信と選択肢が豊富な一般養成施設。どの施設も働きながら、あるいは家庭と両立しながら社会福祉士の受験資格を得て国家試験に合格できるようにサポートしてくれます。
大学を卒業していなくても、実務経験があれば一般養成施設に入れるルートもあるので、一般養成施設で社会福祉士の国家試験受験資格を手に入れてみてはいかがでしょうか。
リジョブケアでは社会福祉士の資格取得後に向け、未経験からでも働ける求人が多数そろっています。自分に合った求人を探して、社会福祉士として働く夢を叶えましょう。