ハイトーンカラー全盛の今、必要なのは正しい教育。カラーのプロを育てたい【 VIF オーナー 田中元さん】#2
ゲストは引き続き、ヘアサロンVIF(ヴィフ)のオーナー・田中元さん。ヘアカラー特化型サロンという信頼感を裏切らない確かな技術と豊富な知識で、リピート率は80%以上という圧倒的な支持を集めています。
後編では、ヘアカラーのセミナー講師としても活躍する田中さんから、教育の重要性について伺います。お客様一人ひとりに寄り添った施術と接客をするために必要なマインドとは?
【お話を伺ったのは…】
VIF (ヴィフ) オーナー 田中元さん

1店舗を経て2014年に「VIF」をオープン。カラーメニューに特化した専門サロンとして人気を集め、その確かな技術力を武器に再来率は80%以上を誇る。年間1,000人以上のヘアカラーを手がける実績から生み出したカラー理論が注目され、セミナー講師としても活躍中。
Instagram:@vif.tanaka
専門サロンであっても、ほかの技術を積極的に学ぶ姿勢を持つこと
――特化型サロンの開業を検討している人が、注意すべき点はありますか?
特定の技術を尖らせることを、逃げの手段として使ってはいけないということ。追い詰められて専門サロンという道を選んだ私が言っても、まったく説得力がないですが(苦笑)。
でも、例えば「カラーが苦手」「縮毛矯正は面倒くさい」といったネガティブな理由でメニューを削っていくと、結果的にお店の可能性を狭めてしまいます。本来なら、体操の内村航平選手のように全種目をハイレベルでこなせる人が、その中でも最も得意なメニューをメインに提供するというのが、専門店の理想形だと思います。
――消去法で安易に選ぶと、潰しが効かなくなるということですね。
これはオーナーだけでなく、お店で働く美容師も同じですよね。自己ブランディングを焦るあまり、槍みたいに一点突破で1つの技術だけを尖らせたって、若いうちはともかく年齢を重ねてからのキャリアの選択肢が限定されてしまいます。
うちのスタッフにもよく話すのですが、もしも苦手な技術があったとしても、全部を100点満点にする必要はないから、せめて学ぶことは諦めないでいてほしい。「できないからもうやらない!」と完全に捨ててしまうのではなく、ある程度の技術力を保ち続けられるよう努力しないと。引き出しが少ない美容師は提案の幅も狭く、魅力的とは言い難いです。

正しい教育を普及し、カラーのプロフェッショナルを増やしたい
――田中さんはインスタで施術のコツやカラーレシピの投稿などをされていますが、どれもすごく詳しい内容で驚きました。
「無料発信するのはもったいない」とご心配の声をいただくこともあります。けれど、本気で技術を習得したいと考えているなら、私の投稿を読めば読むほど「なぜ?」「どうして?」と疑問に思うことが次々に出てくるはず。インスタで見られる小さな動画と一部分を切り取ったテキストだけでは、いくら真似しようとしても同じ仕上がりにたどり着くのは難しいと思います。
そのため、SNSに関しては、美容師がカラー技術をしっかり勉強しようという取っ掛かりになればという気持ちで発信しています。

――ヘアカラーへ苦手意識を持つ美容師さんは多いのでしょうか?
多いなと感じますね。
うちのお店へいらっしゃるお客様の大部分が、複雑なカラー履歴からのリカバリーを必要とする方々です。納得いく仕上がりが得られずサロン巡りを続けた結果、最終的にどうしようもなくなって来店されるパターンがほとんどですが、そもそも修復作業なんて必要としない高クオリティのヘアカラーを提供するのが美容師の勤めであるはず。
けれど、その当たり前のことができていない現実が、日本のサロン業界が抱える大きな課題を物語っています。
――どういった課題でしょうか?
世間ではハイトーンやバイヤレージュがトレンドとなり、お店にはハイレベルなスキルを要求されるオーダーが数多く寄せられています。けれど、カラー技術を体系的に教えられるプロフェッショナルな人材が、圧倒的に不足しているんです。
そのため、多くの美容師が理論的にカラー技術を学べていないまま現在に至っており、個々の勘に頼った「なんとなく」という曖昧な状態で施術しているのが現状。そういった方は後輩にも感覚的な教育しか実践できないため、確かなスキルを備えた美容師が育たないという悪循環が続いています。結果、この歪さのシワ寄せが、すべてお客様に向かっているのが残念でなりません。
――田中さんは、ヘアカラー教育の間口を広げたいという目標をお持ちなんですね。
その通りです。正しいカラー技術を持った美容師を育て、次世代へ正しい教育を行える人を増やしたいという思いから、現在はオンラインも含め年間50本程度のセミナーを任せてもらっています。失敗したカラーヘアに悩むお客様を減らすためにも、私の講師活動がサロン業界を発展させるための一助になると嬉しいです。

お客様への施術説明は必須!知ることは髪を守ることにつながる
――田中さんのセミナーでは、技術面以外のアドバイスもされたりするのですか?
施術を行う上でのマインドは特に重視して伝えます。接客術ともいえるでしょうか。
例えば、高級焼肉店ではお肉の産地やブランドをメニューに表記していますよね。どんなに希少価値があるのかを、店員さんは必ず説明すると思います。それは、高いお金を払ってでも食べて良かったと相手に納得してもらうためには、情報開示が絶対に欠かせないから。
サロンも同様に、妥協しない技術提供をして施術単価を上げるのであれば、なぜこの薬剤を使うのか・この染め方は髪にどんな影響を与えるのかなど、説明責任を果たす必要があると思います。
でも、どうせ理解できないだろうからと、すごく省略した説明で済ませてしまっているお店が少なくないのが残念。難しい専門用語を並べたところで、相手が分からないのは当然です。だったら、分かりやすい言葉で伝えられるようにコミュニケーションスキルを磨くなど、私たちが努力できることはたくさんあるよと話しています。

――マーケティングにおける「顧客教育」の視点ですね。
うちのお店では、新規カウンセリングに30分は時間をかけます。その後も来店の度に施術内容を詳しくお話するため、1年2年と私の元に通ってくれたお客様は、一般的な美容師に負けないくらいの知識を身に付けることになります。
そうすれば、お客様が将来ほかのお店に通うことになった場合も、新しく出会った美容師に対して自分の意見や疑問をきちんと発信することができるはず。「知ること」でお客様が自分自身の髪の毛を守ることにつなげられるよう、私たちはプロとして全力でお手伝いしなければいけません。そしてこの意識こそが、結果的に長く選ばれる美容師になる秘訣だと思います。

――これからヘアカラーの勉強を頑張ろうと思う人にアドバイスをするなら?
ハイトーンカラーのトレンドはしばらく続くと思いますが、同時にナチュラル志向の方も増えてくるのではないかと感じます。限界までブリーチを重ねたお客様から「少し落ち着いた色に戻したい。でもオシャレには見せたい」といったニーズが増えてくるんじゃないかと。
けれど、白っぽくなるまで色を抜いた髪を自然な髪色に戻すというのは、かなり難易度が高い技。一朝一夕で習得できるものではないため、これから新しいスキルに挑戦したいと思う人は「戻しの技術」を頭に置いて勉強してみると良いかもしれませんね。
田中さん流!特化型サロンを成功に導く3つのポイント
1.中途半端は厳禁!覚悟を持ってはじめる
2.ほかの技術も学び続ける意識
3. 専門知識はあますことなくお客様に伝える
取材・文/黒木絵美
撮影/喜多二三雄
Check it

VIF(ヴィフ)
住所:神奈川県横浜市栄区笠間5-27-14
TEL:045-891-2678



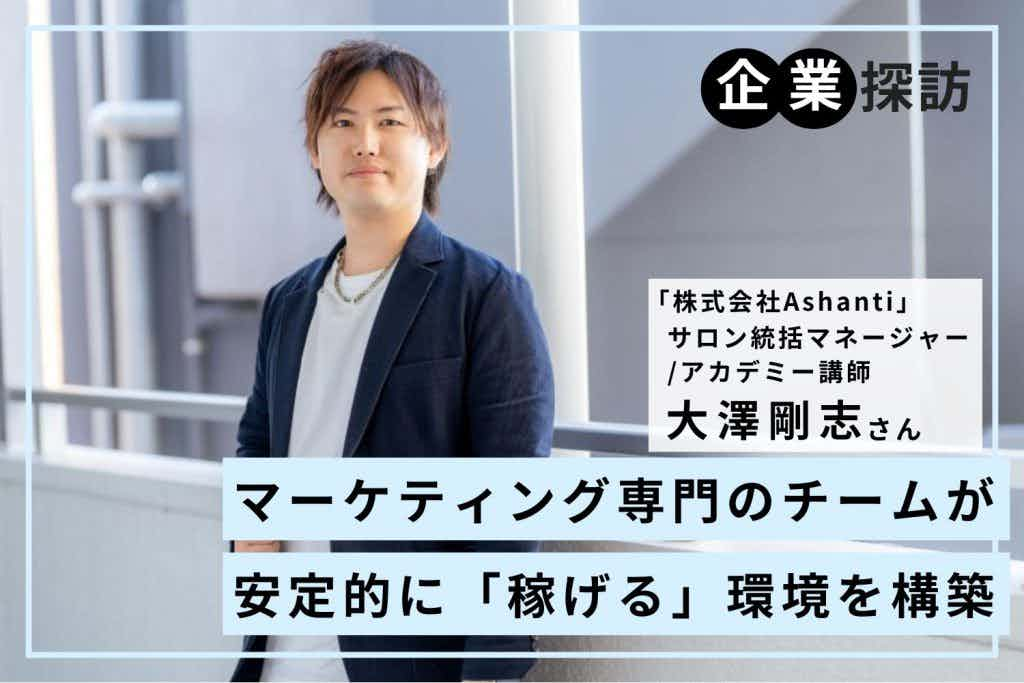
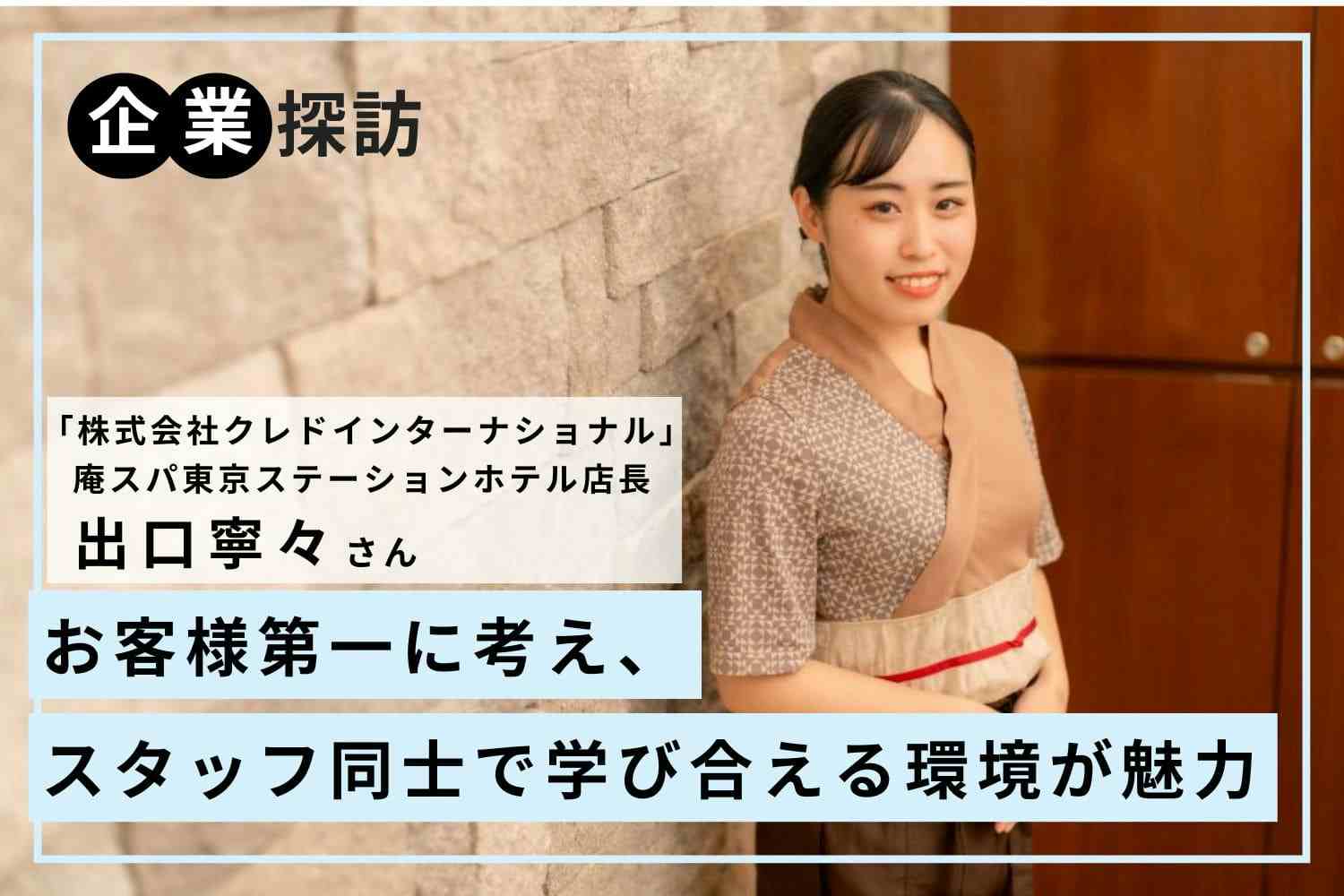
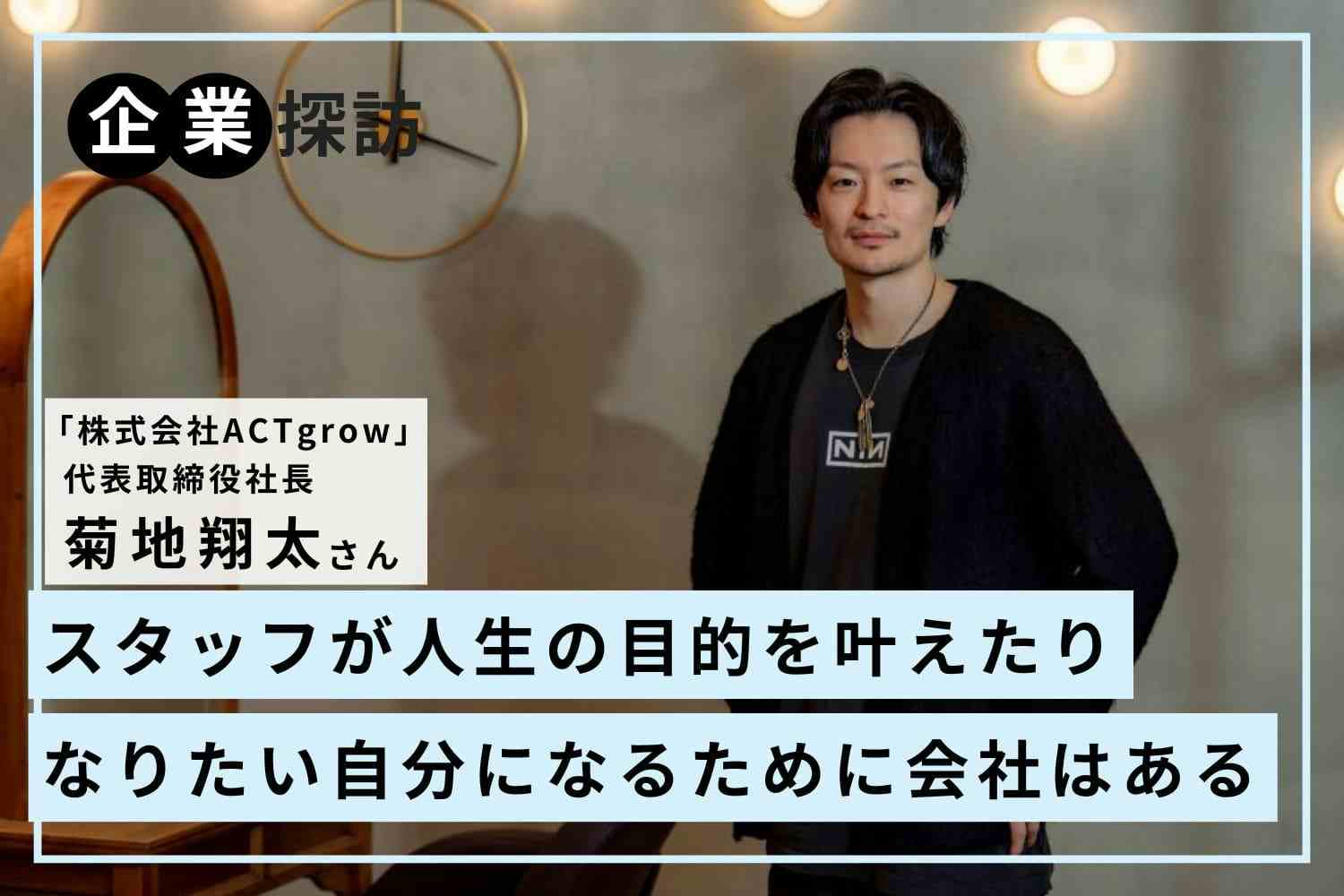
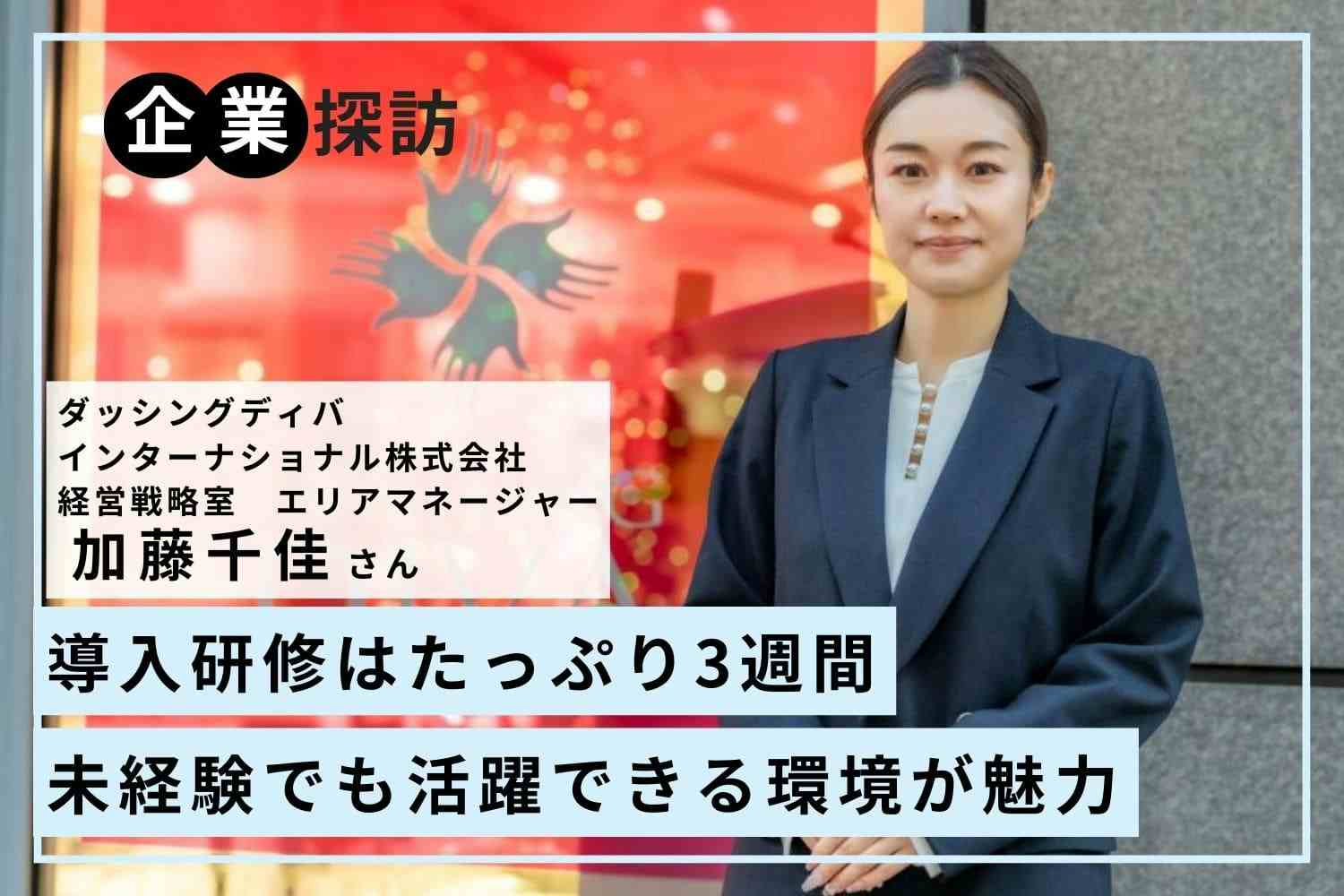
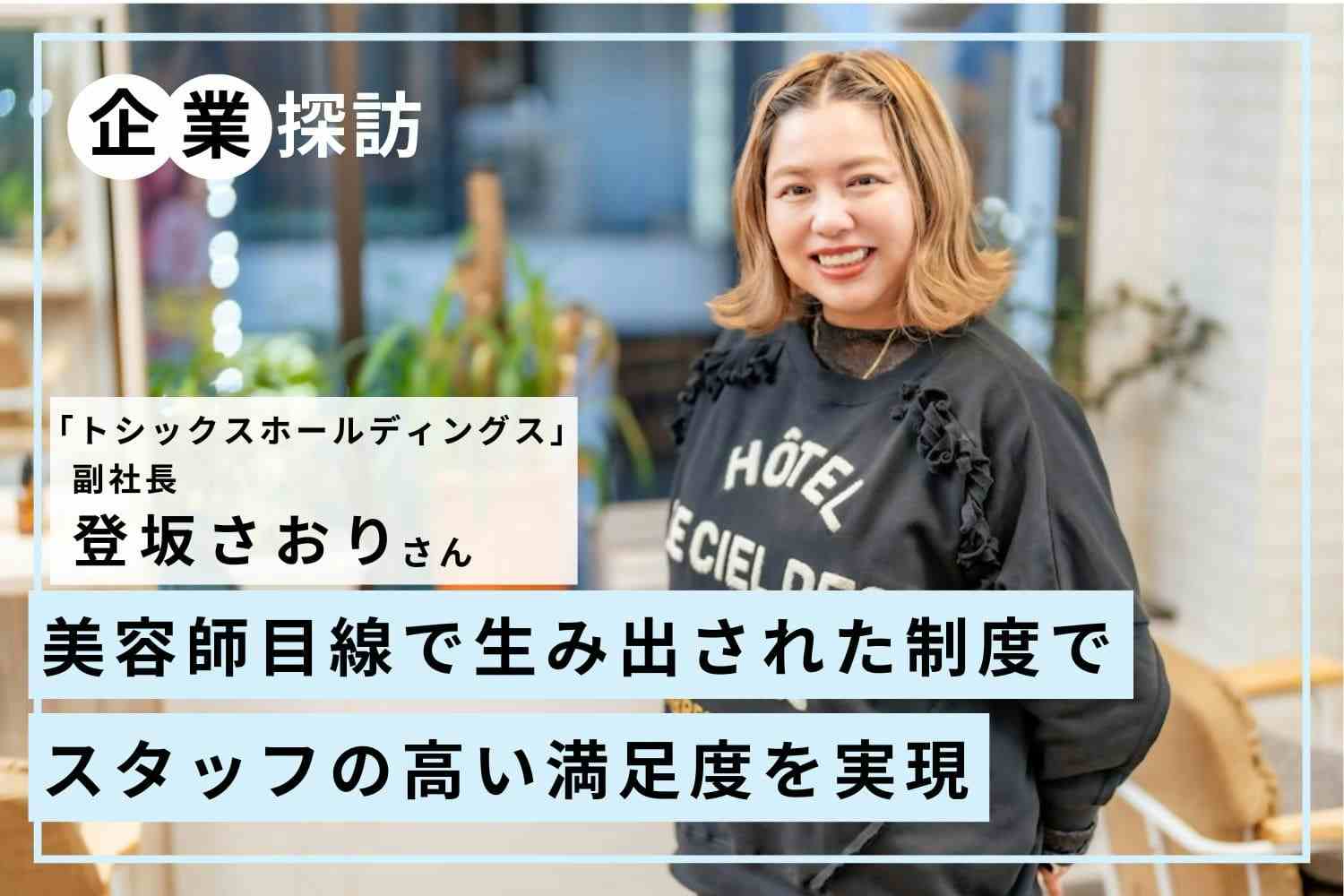
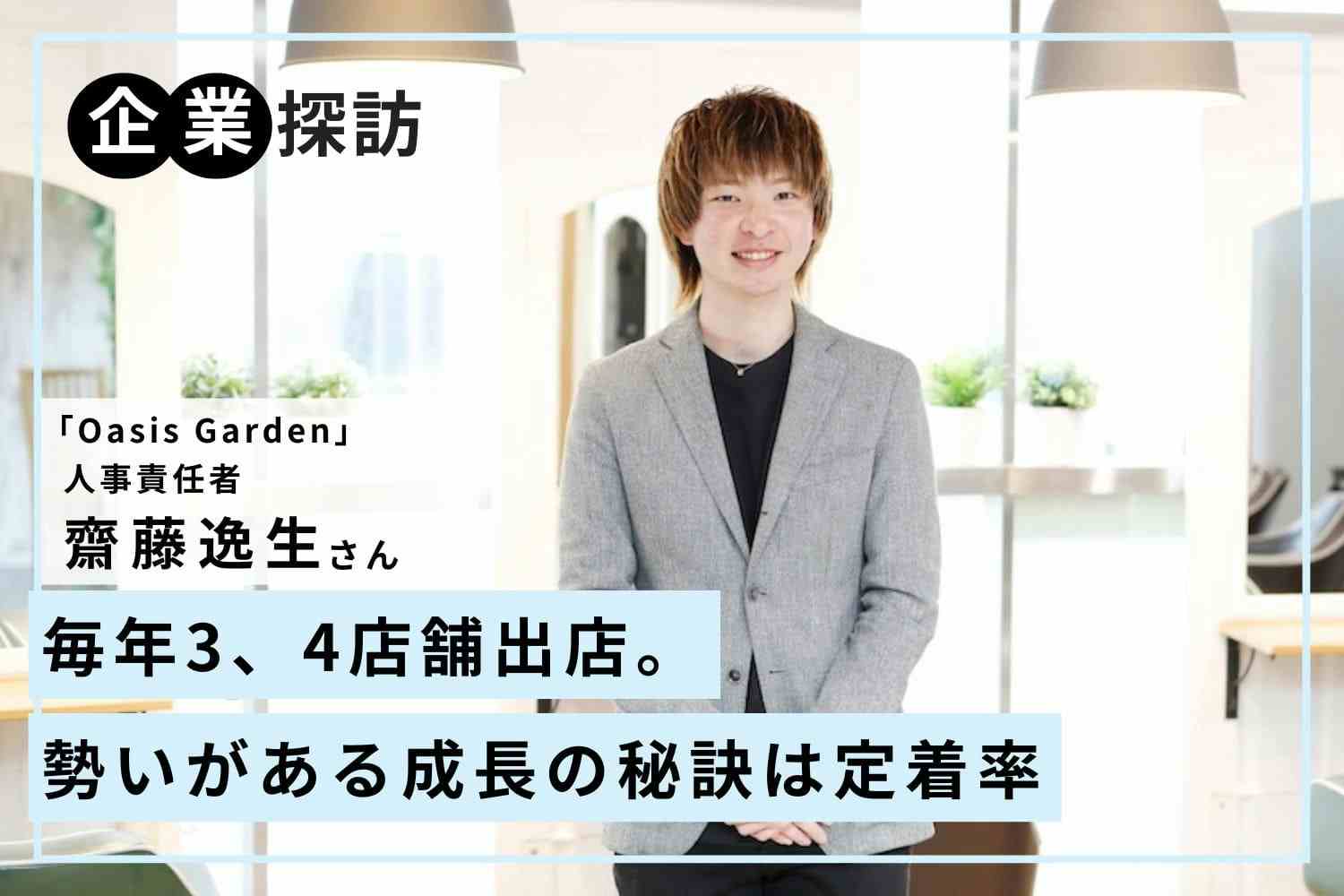

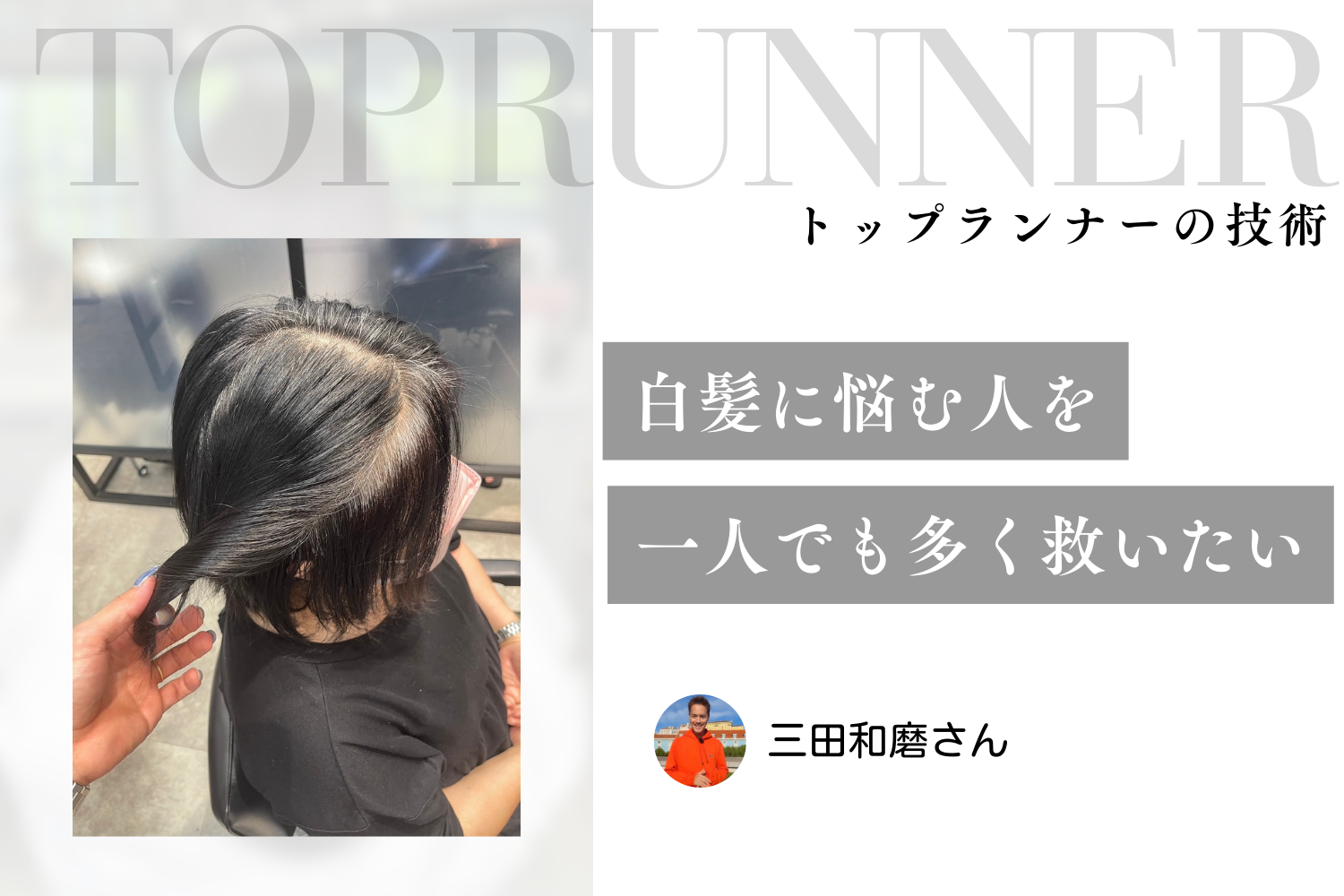

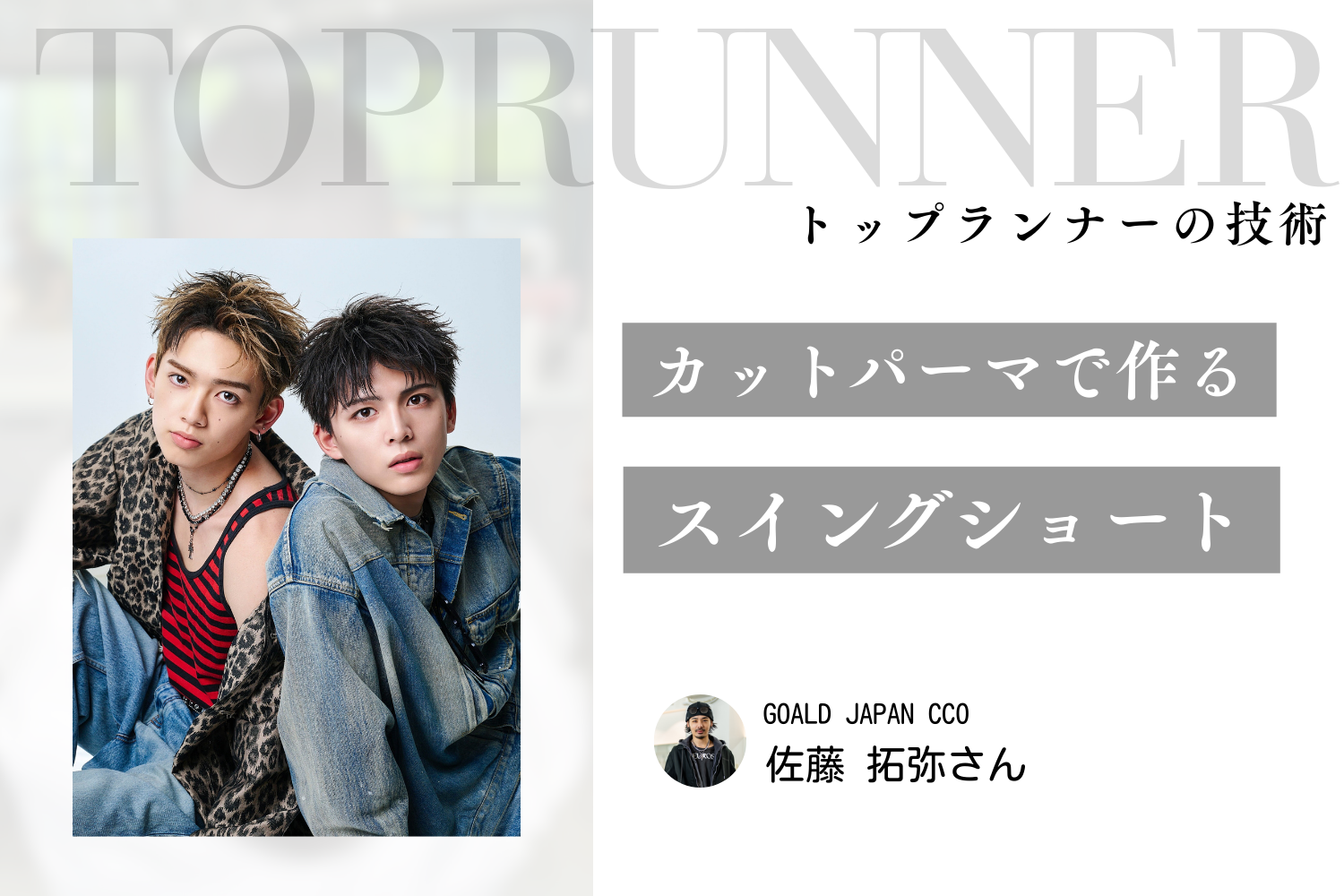
-min.jpg?q=1)
