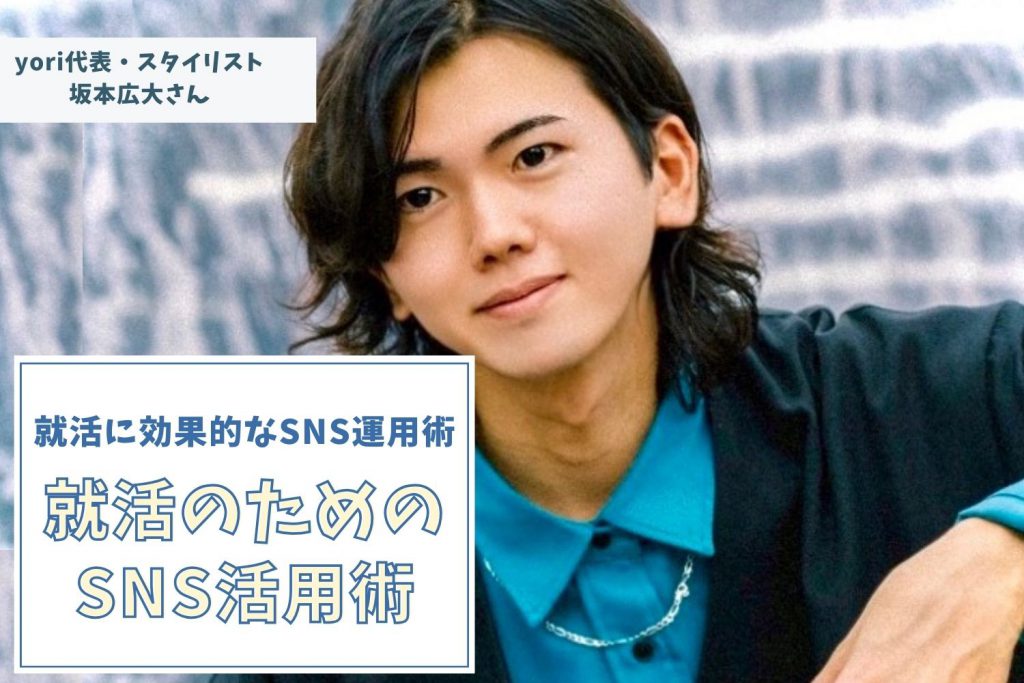アルバイト時代に叩きこまれた「やればできる」の精神が美容業界に入って開花 【美容家 吉川千明さん】♯1
吉川千明さんといえば、リラクゼーションや癒しという言葉がまだなかった時代に、アロマセラピーやオーガニックコスメを日本に広めたオーガニックビューティーの第一人者。意外なことに、千明さんの美容人生は、美容業界からスタートしたものではなかったのだそうです。
バブル期前のリクルートで「やればできる」の精神を刷り込まれた千明さんは、その後転職したイタリアのモダンファニチャー・アルフレックスで、朝から晩まで外国雑誌をスクラップする日々を送ります。30代で美容というフィールドを得たときに、それまでの経験が一気に芽吹き、いくつものサロン経営を成功させることになるのです。
CHIAKI‘s PROFILE
- お名前
- 吉川千明
- 出身地
- 東京生まれ
- 年齢
- 63才
- プライベートの過ごし方
- 仕事とプライベートの堺があまりないけど、天気のいい日に犬と散歩することかな。人に影響力があることは、自分の資産になると思うので、やるべきこととそうでないことをいつも吟味しているんです。買ったまま読めてない本が山ほどあるので、温泉に行ってたまった本でもゆっくり読みたいですね。
- 仕事道具へのこだわり
- 必要だと思うことにはいい先生をつけたり、わたしが時間とお金をかけて体験したことが人のためにもなると思っているんですね。だから、それが仕事道具へのこだわりかな。
ソニープラザのアルバイト時代、驚異の売上を記録

――千明さんといえば、オーガニックビューティーの第一人者ですが、美容の道に入られたのはいつ頃ですか?
最初から美容の仕事に就いたわけじゃないんですよ。わたしは、ただの美容オタクだったの。その時代の母親って目立たない人が多かったけれど、わたしの母はアメ横で海外の化粧品や香水を買ってきて、いつも自分がきれいになることを考えていました。
わたしは、子どものときから母の化粧品を内緒で使っていて、本格的に化粧を始めた大学生の頃から化粧品が大好きで仕方なくなったんです。ブランド品が大好きで、新しい化粧品が出ると香港に買いに行ったり。美容部員さんのアドバイスなしに自分でじっくり化粧品を見たい。ただそれだけの理由でソニープラザでアルバイトを始めました。
ただの大学生のアルバイトだったのに、ものすごく売り上げていたの。
――なぜそんなに化粧品を売ることができたのですか?
目の前に与えられたことを一生懸命やったから。当時流行っていたレブロンの青いマスカラとフューシャピンクの口紅を一生懸命お客様にすすめたら、すごく売上が上がったんです。マーケティング部長に引き合わせたいからと、レブロンの本社のある六本木まで連れていかれたんだから。
――千明さん、かっこいいですね~。
ピュアなんですよ。高度成長期の卸問屋の娘に生まれて、物事を深く考えていなかったんだけど、その分あまり恐怖も与えられていないから、目の前のことにはピュアに取り組めたの。損得勘定の薄い、ピュアな美容オタク。これがわたしの原点です。
――大学卒業後はどうされたのですか?
実家が自営業だったので、就職活動とか上司とかお給料とか、そういう会話を家の中でしたことがまったくなくて。卒業式の日に、友だち全員就職が決まっていてびっくりしたくらい。世間知らずもいいところよね。
卒業した年の秋、「千明ちゃん、いい加減働かないとダメなんじゃない?」と一足先にリクルートで働いていた友人が誘ってくれて、リクルートにアルバイトとして入社しました。そこで配属されたのが、人事教育事業部・研修業務課。さまざまな企業の研修を請け負う部署で、130人のトレーナーが在籍していました。わたしの直属の上司は、その中のトップ。その方に一から教えていただいたことが、非常識だったわたしのその後の人生に大いに活かされることになります。
バブル期前のリクルートで「やればできる」を学ぶ

――リクルート時代は、どんなお仕事をされていたのですか?
いきなりトレーナー向け広報誌制作を任されて、当時は切ったり貼ったりの手作業が大変でした。でも、研修もたくさん受けさせてもらえて、社員と同じように扱ってもらえたのはありがたかったですね。
朝礼で、その日の売上目標を発表し、エイエイオーって気合を入れて、夕方5時になると「目標達成しました」というアナウンスが流れるんです。そうすると、特上寿司が配られてビールで乾杯。バブル期前のリクルートでそんな光景を目の当たりにして、「やればできる」を学んじゃったんですよね。それが完全に刷り込まれているの。
――千明さんのビジネススタイルの原点は、リクルートなんですね。
そうそう。リクルートでは、ひとりひとりの机に「自ら機会を作り、機会によって自らを変える」という標語が掲げられていました。そのため、女性だから、アルバイトだからダメとか、そういう気持ちには全然ならなかったんです。その後の人生は、まさにそれをそのまま実行。素直にね! 高島屋で大きなイベントを大成功させたのも、あのときの学びがあったからなんです。
でも、リクルートの中で生えぬいたわけではないの。わたしはよく学び、よく遊ぶ人だったから。パーティに参加して、ディスコに行って、ドライブして。遊ぶこと命のただのミーハーな女の子。すべてにおいてエネルギッシュでしたね。
いいもの着たい、いいもの食べたい、男の子とデートしたいっていう背伸びの世界。でもそれって、すごい重要なことだと思うんです。20代まではそんなに賢くなくていいと思うの。損得勘定なしに、目の前の与えられた仕事を一生懸命やればいい。
――仕事に遊びに全力投球だったわけですね。リクルートにはどれくらい在籍されたのですか?
25才までです。おバカなわたしが、さすがに何をやるべきか考え始めたんです。当時、インテリアやライフスタイルに興味があったので、いちばんとんがってたアルフレックスというインテリアの会社に本気で入りたいと思って。チャラチャラ遊んでいた恩恵があって、出入りしていたお店の方の紹介で、アルフレックスに併設されていた設計事務所に入社することができたんです。
――そこではどんなお仕事を?
毎日、天井までうず高く積まれた外国雑誌をカッターで切り取ってスクラップしていました。店舗や住宅を建てるときのプレゼンボードをつくる材料ね。朝から晩までインテリアや建築に触れていたことが、後に自分のサロンをつくるときにすごく役立ったんです。
当時学んだことを引き出せたのは30代に入ってから。美容というフィールドを得たときに、わたしの中で地中の種のように埋もれていたものがちゃんと出てきて、すべてに応用が効いたんです。リクルートとアルフレックスにいたことは、わたしのその後の人生において、すごく支えになっています。
純粋に美容が好きだったから、いつもお客様マインド

オーガニックサロンの草分けとなった「白金台ビオパスカル」。
30才で結婚して、その翌年、出産とほぼ同時期にカメラマンの元夫と会社を立ち上げました。ヘアメイクやスタイリストさんとチームを組んで、撮影に関するあらゆることをやる会社ね。わたしは出産後間もなかったので、まずは経理を担当。子どもの成長と共に、わたしも何かやりたいなと考えたときに、やっぱり美容だったんですよ。
当時、自分たちの健康のために分子栄養学を勉強していたので、栄養学に進むか、美容に進むか迷ったんですが、わたしってチャラチャラ生きてきたじゃないですか(笑)。目標を与えられたらがんばるんだけど、パーティに行きたいとか、いい車に乗りたいとか、チャラチャラしてるんですよ、すべてが。どうも栄養学の人たちとはノリが違うな。わたしは、楽しくレブロンの口紅を売れる人なんだから、きれいになることで元気になれるほうがわたしらしい。それで、美容の道を選びました。
――その見極める力が素晴らしいですよね。
ビジネスだけのために起業する人っていっぱいいるんですけど、わたしはそういうのが嫌だったのね。
――美容で起業をすることを決めて、まずは何から始めたのですか?
当時のエステといえば、脱毛と痩身の大手サロンが主流でしたが、わたしのノリじゃなかったから、エステには一回も行ったことがなかったの。脱毛と痩身以外のエステティックを調べていくうちに、CIDESCOという国際ライセンスがあることを知ったんです。
CIDESCOをとるために、老舗の理美容用品商社・滝川が運営する美容学校に入りました。子どもを保育園に預けてから、自転車で勝鬨橋を渡って、最後の授業の後にモップがけをして。それからまた勝鬨橋を自転車で渡って、子どものお迎えはいつも最終の19時でしたね。
――お子さんがまだ小さいときの通学はかなり大変だったと思います。そこではどんなことを学んだのですか?
生理解剖学からメイクアップまで美容のあらゆることを身につけました。わたしはナチュラル派だと思われていますが、すべてのマシンが使えるんですよ。皮膚構造はいまも当時も変わらないでしょ。その後30年、美容業界でビジネスできているのは、当時の学びがあったからだと思います。
――とくに印象に残っている授業は?
ストレスという言葉も、リラクゼーションという言葉も世の中にない時代に、アロマセラピーやタラソテラピーと初めて出会ったときは衝撃的でしたね。通常の授業の他に、アロマとタラソの授業をオプションでとって勉強したんですけど、どんどん興味が湧いてきて。お金と時間を使って新しいものを体験して、映像を見て、自分でも施術をやり始めました。アロマとタラソは、知れば知るほど増々わたしに響いてきました。
――その後もアロマとタラソの学びを深めたのでしょうか。
まだ子どもが小さくてエステ修行に行けなかったので、すぐに月島にサロンを開いたんです。授業だけでは分からないこともあるし、もっともっと学びたかったので、いいエステティシャンを引き抜いて、働いてもらったの。
――それはレアなスタイルですよね?
でしょ。生の施術を見せてもらうわけ。素人目線だったからこそ、どうしてそうするの?とか、わたしだったらこうするなということがたくさんありました。純粋に美容が好きだったから、いつもお客様マインドなんですよ。当時、エステティシャンって決まって白衣を着て、ワゴンも色気のない白いものだったの。でもわたしは、アンティークショップで購入したキャビンに穴を開けて、白衣ではなくてバティックを着てみたり。お客様目線だったからこそ、自由な発想でもっと素敵な空間にしようと取り組んでいました。
――千明さんも施術されていたのですか?
わたし、エステはものすごくやったんですよ。いまこそやってないけど、コロナ前までは月一回は現場で施術してましたよ。フェイシャルもボディも誰よりも上手いよ(笑)。最初から上手にできる人もいるけど、わたしはダメ出しされるほうなの。でも最終的には上手くなる。それは、お金と時間を使って、ものすごくいい先生のお客にもなり、レッスンも受けてきたから。
まだ日本では珍しかったアロマテラピーやタラソテラピーはメディアにも取り上げられるようになり、いいエステティシャンも育って、サロンは常に満席状態でした。これが白金台のビオパスカルというサロンになり、日本でいちばん憧れのサロンとして紹介されることになります。
後編では、ジュリークショップの日本展開、日本初の女性専用漢方薬局やオーガニックコスメのPRルームなど、独自の目線のビジネス展開についてお伺いします。
取材・文/永瀬紀子